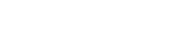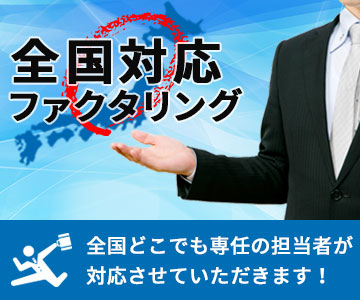運転資金の主な融資先とは? 借り入れ目安や融資を受ける際のコツをご紹介
最終更新日:2025年09月26日
企業の経営者や財務部門担当者の方に向けて、融資で運転資金を調達する方法を解説します。各金融機関で運転資金を調達する際のメリットやデメリットもご紹介しているので、自社に適した融資先を見つけられるでしょう。
企業を存続させるために欠かせない運転資金。自己資金で用意してもよいですが、中小企業やベンチャー企業では、融資を利用することもあります。しかし、融資では「どれくらいの金額を借りるべきなのか」「どこから借りるべきなのか」といったさまざまな不明点が出てくるでしょう。
そこで本記事では、運転資金の種類や融資先、借り入れ額の目安などを解説しています。融資を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
<この記事で分かること>
・運転資金の定義
・運転資金の種類とそれぞれの概要
・運転資金を調達できる主な融資先
・運転資金の借り入れ目安や計算方法、審査通過のコツ
Table of Contents
運転資金とは?
運転資金は、企業や個人が事業を存続させるために必要な資金です。具体的には商品の仕入れや事務所の家賃、水道光熱費、人件費、外注費などに充てる資金が該当します。運転資金が不足すると、帳簿上黒字が出ていても事業を続けるのが難しくなります。
事業を安定させるために必要な運転資金の目安は、平均月商の3~6カ月分です。建設業や不動産業などは売掛金の回収サイトが他業種と比べて長い傾向にあるので、多めに用意しておくとよいでしょう。
運転資金の種類
運転資金は使用目的によって、以下の5種類に分類できます。
1.経常運転資金
2.増加運転資金
3.減少運転資金
4.季節運転資金
5.設備未払金決済運転資金
運転資金を融資で用意する場合は、この分類をしっかりと把握しておきましょう。それぞれについて詳しくご紹介します。
経常運転資金
経常運転資金は、企業が現在行っている事業を維持・継続するために必要な資金です。具体的には、商品や材料の仕入れや人件費、家賃、光熱費のための資金などが該当します。一般的に運転資金といえば、経常運転資金を指すことが多いです。
増加運転資金
増加運転資金は、売り上げが増加しているときに必要な資金です。売り上げの増加は企業にとって望ましいことですが、売り上げが増えると経費も増える傾向にあります。例えば、売り上げの増加に対応するために商品の生産数を増やせば、材料の仕入費用が増えます。さらに人を新しく雇えば、人件費も増えるでしょう。
増加運転資金が不足するとさらなる売り上げ増加の機会を逃してしまう可能性があります。最悪の場合、黒字が出ているにもかかわらず事業が続けられなくなる「黒字倒産」に至る恐れもゼロではありません。売り上げが順調に伸びているときこそ、潤沢な資金が必要なことを覚えておきましょう。
減少運転資金
減少運転資金は、売り上げが減少しているときに必要な資金です。売り上げが減少すると仕入れなどの変動費は減りますが、人件費や家賃などの固定費はほとんど変わらずに発生し続けます。また変動費の減少以上に売り上げが減れば、資金繰りは悪化します。この状況を乗り切るためのつなぎ資金が、減少運転資金です。一時的に売り上げが減少しても、十分な減少運転資金があれば事業を継続できます。
ただし、売り上げの減少が続くと、いずれは減少運転資金すら用意できなくなります。事業が立ちゆかなくなる前に、固定費の削減や新たな販路開拓などの経営立て直しを進めましょう。
季節運転資金
季節運転資金は、特定の季節や時期だけに発生する費用をまかなうための資金です。例えば、エアコンなど特定の季節によく売れる商品を取り扱っている場合、その季節だけ仕入れを増やしたり短期で人を雇ったりするため、普段以上に資金が必要になります。
その他、従業員にボーナスを支払う時期や、法人税などを納める時期にも季節運転資金が必要になるケースもあります。これらの出費は予測しやすいため、事前に資金を用意する手段を確保しておきましょう。
設備未払金決済運転資金
設備未払金決済運転資金は、設備や機器などを購入・リースで導入したものの、何らかの事情で半年以上代金を支払えなかった場合に発生する資金です。
工場や店舗などの設備や機器は通常、資金の目途を付けた上で設備資金で導入します。しかし、業績の悪化などで支払いが滞り、半年経っても未払い分がある場合は、それに充てる資金を設備未払金決済運転資金として区別します。
設備未払金決済運転資金の存在は金融機関から融資を受ける上での足かせとなるため、早めに支払いましょう。
運転資金の融資先
後先考えずに借り入れを行うのは避けるべきですが、適切な金額で融資を受ければ、事業の拡大速度を速められる可能性があります。融資先によって金利や借入上限額、審査基準などが異なるため、自社の状況に適したところを選びましょう。
銀行
運転資金の融資先として特にメジャーなのが銀行です。銀行には都市銀行や地方銀行、インターネット銀行などがあります。運転資金の融資を受ける場合は「プロパー融資」と「信用保証付き融資」のどちらかを利用します。
プロパー融資は公的機関である信用保証協会の保証がない、銀行が直接融資する制度です。金利は低い傾向にある一方で審査が厳しく、実績の少ないベンチャー企業や中小企業は簡単には利用できません。
信用保証付き融資は、前述の信用保証協会が支払いを保証する制度です。万が一、債務者が支払えなくなった場合、信用保証協会が銀行に立て替えを行います。利用者は見返りとして、信用保証協会に信用保証料を支払います。銀行の負うリスクが低いため中小企業などでも利用しやすいですが、利息とは別に信用保証料も払わなければなりません。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、国が100%出資している政府系の金融機関です。一般の金融機関を補う役割を担い、さまざまな目的に対応した融資を提供しています。
日本政策金融公庫の金利は低めです。無担保・無保証人で借りられる制度もあるため、保有資産に乏しい企業でも利用できます。支払期間も長めに設定できるので、無理のない完済計画を立てやすいです。
一方で、支店は全国で152店舗しかないため、企業の所在地によってはアクセスに手間がかかるかもしれません(※)。山梨や徳島など、1店舗しかない県もあります。なお、沖縄は日本政策金融公庫の支店がなく、かわりに沖縄振興開発金融公庫が業務を行っています。
※参考:日本政策金融公庫.「民間金融機関との連携の取り組みについて」.
信用金庫
信用金庫は、特定の地域の住民や事業者のための金融機関です。銀行に近い機能を有していますが、銀行が株式会社の形態を取る営利法人であるのに対して、信用金庫は会員の出資による非営利法人です。原則として、会員(地域内の住民や規模の小さい事業者など)でなければ融資が受けられません。
信用金庫は地域の小規模事業者や中小企業に対しても、積極的に融資を行っているため、銀行で断られた企業でも借りられる可能性があります。また経営相談や事業承継支援などのサポートも充実しています。
一方で、金利は銀行と比べるとやや高めで、融資限度額も少ないため、多額の借り入れには向きません。
ノンバンク
ノンバンクは、預金を扱わず融資を行う金融機関の総称です。具体的にはクレジットカード会社や信販会社(ショッピングローンなど、代金の立て替えを行う会社)、消費者金融などが該当します。
ノンバンクを利用するメリットは、必要書類が少なく審査スピードが早い傾向にあることです。多くのノンバンクは融資希望者の信用度をスコア化する「スコアリングシステム」を採用しています。自動で信用度などが計算されるのでスピーディに進められるのです。
一方で、ノンバンクは銀行や信用金庫と比べると金利が高い傾向にある他、融資限度額は低めです。短期的なつなぎ資金を用意する際には便利ですが、大がかりな投資には向きません。
地方自治体
地方自治体や金融機関、信用保証協会の3者が連携して提供する融資の仕組みを制度融資といいます。基本的な仕組みは銀行の信用保証付き融資に似ていますが、地方自治体が信用保証料の一部を補助したり、金融機関に対して貸付資金を一部預託したりするという特徴があります。
制度融資では、長期かつ低金利での借り入れがしやすいという点がポイントです。地方自治体が貸付原資を預託していたり、信用保証料を一部払ってくれたりするため、利用者の負担が少なく済むでしょう。場合によっては、担保や保証人が不要なこともあります。
一方で、3者が関わるため審査に時間がかかります。制度融資で資金を調達したい場合は、早めに準備しましょう。
運転資金の借り入れ期間の目安
運転資金の借り入れ期間の目安に、債務償還年数があります。債務償還年数は金融機関が重視する指標の一つです。債務償還年数は、以下の式で求められます。
・債務償還年数 = (借入金-正味運転資金)÷(経常利益+減価償却費-法人税など)
・正味運転資金 = 売掛金+受取手形+棚卸資産-支払手形-買掛金
正味運転資金とは、流動資産から流動負債を差し引いた額です。1年以内に現金化できる資産と、1年以内に支払いが必要な負債の差額であり、企業の短期的な資金余力を測る指標ともいえます。債務償還年数の計算式の(借入金-正味運転資金)の部分は、借入金から正味の現金を除いた、流動資産を全て支払いに充てても残る実質的な借入額です。
一方、計算式の(経常利益+減価償却費-法人税など)の部分は、経常的な利益を意味します。債務償還年数は実質的な借入額が多く、経常的な利益が少ないほど長くなります。
当然ながら、債務償還年数は短いに越したことはありません。一般的に7年程度なら健全、10年なら健全の上限、10年超は借り入れが多い状態、20年超は抜本的な改革が必要な状態といわれています。債務償還年数が10年を超える借り入れを求める場合は、完済計画や事業計画書をしっかりと作る必要があります。
運転資金の計算方法
運転資金の計算方法は大きく「在高(ありだか)方式」と「回転期間方式」に分けられます。
在高方式による運転資金の計算方法は以下の通りです。先述した正味運転資金の計算式と同様です。
・在高方式による運転資金 = 売掛金+受取手形+棚卸資産-支払手形-買掛金
正味運転資金は簡単に計算できますが、大まかな運転資金しか分かりません。より正確に計算したい場合は、回転期間方式で求めます。回転期間方式での計算式は以下の通りです。
・回転期間方式による運転資金 = 平均月商×(売上債権回転期間+棚卸資産回転期間-買入債務回転期間)
・売上債権回転期間 = 売上債権÷(年間売上高÷365日)
・棚卸資産回転期間 = 棚卸資産÷(年間売上原価÷365日)
・買入債務回転期間 = 買入債務÷(年間売上原価÷365日)
売上債権回転期間は売上債権を1日の売り上げで割った期間、棚卸資産回転期間は棚卸資産を1日の平均売上原価で割った期間、買入債務回転期間は買入債務を1日の平均売上原価で割った期間です。売上債権の回収が遅い、在庫がはけるペースが遅い、買入債務の回収が早いといった特徴があると、運転資金の金額は高くなります。
融資を受ける際のコツ
ここからは、実際に融資の審査を受ける際のコツをご紹介します。
資金の使い道を明確にする
資金の用途を他者に説明できるくらい明確にしておけば、金融機関からの信頼を得やすくなります。先述した通り、運転資金にはいくつか種類があるため、どれに該当するのかを考えておきましょう。用途が不明瞭であったり、事業計画書と口頭での説明の整合性がなかったりすると、審査に通りにくくなります。
現実的な事業計画書を作成する
融資の審査で重視されるのが、事業計画書です。事業計画書には事業の方向性や目標、予測業績などを記載します。金融機関は事業計画書の内容を基に、事業の将来性や支払い能力を審査します。説得力のある事業計画書を用意できれば審査で有利になる一方で、矛盾や根拠に乏しいと見なされれば審査で不利になるでしょう。
金融機関が事業計画書のテンプレートを用意している場合は、それに従って記入してください。テンプレートが特に用意されていない場合は、他の金融機関やコンサルティング会社が公開しているテンプレートを参考にするとよいでしょう。
必要書類を不備なく準備する
必要書類は金融機関によって異なります。基本的に条件面が優れている融資の場合は審査が厳しく、必要書類が多いです。先述した事業計画書の他、決算書や資金繰り表なども求められることが多いため、事前に準備しておきましょう。また、提出前に記載漏れやミスがないかを確認することも大切です。
ある程度の自己資金を準備しておく
自己資金がほとんどない状態だと、支払い能力を疑われてしまうかもしれません。融資に当たって明確な基準額はありませんが、ある程度まとまった自己資金を準備しておくのがよいでしょう。
担保や保証人の準備をしておく
担保や保証人がなくても借りられる融資もありますが、あった方が金利や借入額などの条件面で有利になりやすいです。担保としての価値が高いのは不動産ですが、商品在庫や売掛金など流動性の高い動的資産を担保にしたローンもあります。担保にできるものがある場合は、それに関する資料も用意しておきましょう。
まとめ
企業や個人が事業を継続させるための資金を運転資金といいます。運転資金にはいくつか種類があり、中でも事業を維持存続するための経常運転資金を確保しておくことは、特に重要です。月商の3~6カ月程度の運転資金が確保できれば、倒産のリスクをある程度減らせるといわれています。
運転資金は自己資金でまかなうこともできますが、融資で用意しても問題ありません。主な融資先は銀行や日本政策金融公庫、信用金庫、ノンバンクなどです。どこから借りる場合でも、資金の用途を明確にした上で適切な事業計画を立てておきましょう。
ただし、融資には時間がかかるという欠点もあります。より素早く資金調達したい場合は、売掛債権を売却するファクタリングを利用するのも方法の一つです。即日入金に対応しているファクタリング会社も多く、急な資金不足のときには役に立つでしょう。
株式会社Mentor Capitalは、審査通過率92%の柔軟な対応が特徴のファクタリングサービスを提供しています(※)。最短即日で現金化できる上に、赤字や債務超過、税金滞納の場合にも対応できる可能性があるので、まずはお気軽にご相談ください。
※参考:株式会社Mentor Capital.「即日資金調達のファクタリング会社 | 株式会社Mentor Capital」.