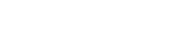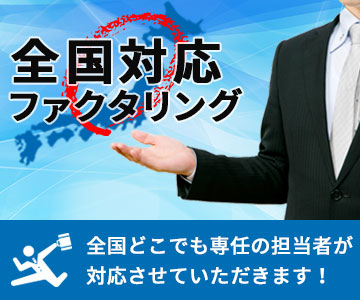資金繰りの悪化によって起こり得るリスクとは? 悪化の理由や改善方法を解説
最終更新日:2025年09月26日
企業の資金繰りが悪化する主な理由や、改善方法を解説しています。資金難や慢性的な赤字に悩まされている方、経営を安定させたい方は参考にしてください。
帝国データバンクの調査によると、2024年に休廃業した企業の51.1%は直近損益が黒字でした(※)。損益計算書上で黒字が出ていても手元の資金が枯渇すれば、日々の支払いができずに企業は倒産してしまいます。
そこで本記事では、資金繰りが悪化する主な理由や改善方法などを解説します。資金繰りが悪化してお困りの経営者の方や企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
<この記事で分かること>
・資金繰りが悪化することで起こり得るリスク
・資金繰りが悪化する主な理由
・資金繰りを改善する方法
※参考:帝国データバンク.「「全国休廃業・解散」動向調査」.
Table of Contents
資金繰りとは?
資金繰りとは、会社に出入りする資金の流れを管理し、必要に応じて過不足を調整することです。今手元に資金がどれくらいあるのか、いつどこからどれだけの資金が流入し、どこへ流出していくのかを把握しておけば、資金が不足するリスクを軽減できます。
なお、ここでいう資金とは、以下のような現金や現金同等物(容易に現金化できて価格変動リスクが少ない資産など)を指します。
・現金
・普通預金
・当座預金
・通知預金
・定期預金
・譲渡性預金
・コマーシャルペーパー(企業が短期で発行する無担保の約束手形)
・売戻し条件付現先(買い戻しの約束がある債券)
・公社債投資信託
ここに含まれないもの、例えば株式や不動産などは帳簿価額にかかわらず資金には算入しません。資金は会社が生き続けるために必要な血液のようなものであり、流れが滞れば経営が傾いてしまうかもしれません。余裕を持った資金繰りを心掛けましょう。
資金繰りとキャッシュフローの違い
資金繰りと類似した概念にキャッシュフローがあります。キャッシュフローも資金の流れを指すという点では同じですが、目的や把握する対象が異なります。
資金繰りの目的は、資金を枯渇させないことです。把握したい対象は現在から近い未来にかけての資金の流れです。資金繰りをすることで少し前の資金の流れや現在の入出金の予定を基に、近い将来の資金の流れを予測します。
一方でキャッシュフローの目的は、現時点での財務健全性や成長可能性を評価することです。把握したい対象は過去から現在にかけての資金の流れです。資金がいつどれだけ増減したかが分かれば、売り上げの目標や経営課題が設定しやすくなります。
資金と利益の違い
先述した通り、資金とは現金や現金同等物のことです。一方、利益とは収益から費用を差し引いた、企業のもうけの額です。利益にはいくつか種類があります。例えば、売上高から売上原価を差し引いた金額は売上総利益(粗利)と呼ばれ、企業の経営状態を把握する重要な指針として知られています。
資金と利益は、必ずしも一致するとは限りません。例えば商品を現金3,000円で仕入れて、掛取引にて5,000円で販売したとします。この場合の売上総利益は「5,000円 – 3,000円」で2,000円です。一方で掛取引を行ったため、その時点では現金収入は発生せず、資金は-3,000円となります。利益が増加したにもかかわらず、資金が減少していることが分かるのです。
資金繰りが悪化すると黒字倒産のリスクがある
利益は増えるものの、資金が減るような取引が重なった場合、損益計算上は黒字であるにもかかわらず事業に必要な経費(人件費や買掛金など)が払えずに倒産する「黒字倒産」が起こり得ます。
企業間の取引では、売り上げが発生してから入金されるまでに一定の期間が空く、掛取引が行われるケースが多いです。掛取引では、回収サイト(売り上げ発生から入金までの期間)が長かったり、支払いサイト(仕入れの発生から支払いまでの期間)が短かったりすると、黒字倒産の可能性が高まるため注意が必要です。
資金繰りが悪化する主な理由
資金繰りが悪化する理由を理解していなければ、適切な対策を講じることはできません。ここでは企業の資金繰りが悪化する主な理由を解説します。
赤字状態の継続
赤字とは、収入よりも支出の方が多い状態のことです。先述の通り黒字でも倒産することはありますが、赤字だとより倒産のリスクは高まります。
もちろん、事前に資金を用意していれば、短期間の赤字には耐えられるでしょう。しかし赤字の期間が長くなれば、蓄えた資金もいずれ枯渇してしまいます。赤字が常態化している場合は、現状を分析した上で、具体的な改善策を立てましょう。
売り上げが大幅に減少
売り上げの大幅な減少も、資金繰りの悪化につながります。売り上げが減少すると仕入費用などの変動費は少なくなるものの、家賃や人件費などの固定費はほぼ変動しません。必然的に資金繰りは厳しいものになります。また、売り上げが減少すれば当然赤字にもなりやすくなるため、先述した「赤字状態の継続」につながります。
なお、売り上げが減少する要因は、内的要因と外的要因に分類可能です。内的要因は企業自体に起因するもので、新規顧客の減少やリピート率の低下、従業員の質の低下などが挙げられます。外的要因は企業の外部に起因するものであり、流行の変遷や、強力な同業他社の登場、市場全体の縮小などが挙げられます。いずれにせよ早めに原因を突き止めて対策をしましょう。
売り上げが大幅に増加
売り上げの大幅な増加も、資金繰りの悪化につながることがあります。売り上げの増加は一般的に利益の増加につながりますが、利益が増えたからといって必ずしも資金が増えるとは限りません。特に売り上げ増加のために仕入れや人件費などを増やす場合は、注意が必要です。
掛取引がメインの場合、売り上げが増加しても実際の入金にかかる時間は変わりません。一方で入金よりも先に出ていく仕入れ費用や人件費が増加すれば、膨大な売掛金があるにもかかわらず資金が枯渇してしまう可能性もあります。売り上げの他に費用も増加している場合は、回収サイト・支払いサイトにも気を配ることが大切です。
コストの高騰
コストとは、要するに費用のことです。企業が支払うコストは、固定費と変動費に分けられます。固定費は、販売や製造とは直接関係がない費用です。具体的には人件費や家賃、水道光熱費などが該当します。
一方で変動費は、売り上げの変化に伴って上下する費用です。具体的には原材料費や輸送費、販売手数料などが該当します。
固定費と変動費、どちらも社会情勢の影響で変動し、高騰すれば資金の減少につながります。それぞれを削減しようと取り組むことはよいことですが、基本的には固定費の削減の方が対策しやすいです。例えば、オフィスの郊外移転・規模縮小による家賃削減、時間外労働の削減、外注化による人件費の抑制などの手段が考えられます。
取引先からの入金遅れ
掛取引を行っている場合、取引先の資金繰り悪化により入金が予定日より遅れることがあります。売掛金が予定通りに入金されることを前提に資金繰りを考えていると、このような不測の事態に対応できません。連鎖倒産を防ぐためにも、資金繰りには常に余裕を持たせておきましょう。
なお、仮に取引先が倒産しても、即座に売掛金が消滅するわけではありません。売掛金という債権は残り、倒産したとしても債務を果たす義務があります。しかし法的な義務があったとしても、満額を回収するのは難しいかもしれません。少しでも損失を減らすために、買掛金などの債務がある場合は相殺する、担保権がある場合は行使するなどの対応を取るようにしましょう。
資金繰りを改善する方法
ここからは、資金繰りを改善する具体的な方法をいくつかご紹介します。
事業を改善する
資金繰りを改善する上で特に大切なことは、事業の改善です。現時点で自社の事業にどのような問題点があるかを洗い出し、問題点に対する改善を図ります。赤字が続いている場合は、新たな販路拡大や経費削減で黒字への転換を図りましょう。他にも業務フローを見直したり、内製と外注を必要に応じて使い分けたりするなど、さまざまな手段があるため、自社に適した方法を選んでください。
資金繰り表を作成・活用する
資金繰り表とは、一定期間における資金の流れをまとめた表です。資金繰り表を作成すると、将来資金がどのように増減するかを可視化できるため、資金繰りの計画を立てやすくなります。また、資金繰り表によって、現在の財務体質の問題点が見つけやすくなるという点もポイントです。例えば売掛金の回収までの期間が長過ぎたり、買掛金の支払いまでの期間が短過ぎたりする場合は、その条件を見直すことで改善できます。
資金繰り表の作り方
資金繰り表を作成する場合は、まずはテンプレートを入手しましょう。資金繰り表には決まった形式がないため、一から作ることもできます。ただし初めて作成する場合は、既存のテンプレートを活用した方が間違いを防ぎやすいでしょう。経理システムに組み込まれているものや、Web上で公開されているExcel形式のものもあるのでチェックしてみてください。
テンプレートが手に入ったら、作成に必要な資料を用意します。一般的には、以下の資料が必要です。
・売掛金や受取手形の入金予定が分かるもの
・買掛金や支払手形の出金予定が分かるもの
・金融機関からの借入金の支払い予定が分かるもの
上記の資料を基に、資金繰り表の記入を進めていきます。資金繰り表には、既に経過した月(実績)の資金の出入りと、将来の月(予測)の資金の出入りを記入します。前月の入出金額の実績から今月の入出金額を予測し、それを基に来月の入出金額を予測する、という流れです。この際に少し厳しめに予測を立てておくと、資金繰りの悪化につながりにくいでしょう。
なお、資金繰り表は、大きく日次(日繰り表)、月次(一般的な資金繰り表)、年次に分けられます。月次を優先的に作成することが一般的ですが、資金繰りが厳しい場合は日次も作成して、1日単位で資金の増減を確認するのもよいでしょう。
経費を削減する
適切な経費の削減は資金繰りの改善につながりますが、やみくもに経費を削るのは逆効果になる可能性があるので注意してください。経費を削減した結果、商品やサービスの質が悪化したり、従業員のモチベーションが低下したりすれば、経費以上に売り上げが減少してしまうかもしれません。売り上げや利益につながっていない経費を洗い出し、従業員の理解を得ながら削減していきましょう。
遊休資産や不良在庫を見直す
遊休資産とは、事業のために取得したにもかかわらず何らかの理由で使用していない資産です。具体的には、使っていない土地や建物、稼働していない機械設備などが該当します。
不良在庫とは、そのままでは売れる見込みが乏しい在庫で、生産し過ぎた商品や流行遅れの商品、賞味期限切れの食品などが該当します。
土地や建物、機械などの遊休資産は持っているだけで固定資産税や管理費用などの経費が発生するため、今後も使う予定がない場合は早めに処分しましょう。売却すれば経費を削減しつつ資金も得られて一石二鳥です。
不良在庫はそのままにしておくと保管スペースを圧迫する上に、食品などの場合は販売可能な在庫にまで腐敗が及ぶリスクがあります。値引きや廃棄などをして、なるべく早く在庫を減らしましょう。
資金調達をする
資金繰りの悪化が一時的なものであれば、資金調達によって乗り越えられる可能性があります。資金調達とは、事業の運営や成長のために必要なお金を外部から集めることです。
資金調達の中でも、一般的な方法が金融機関からの借り入れです。銀行や信用金庫などの民間金融機関の他、日本政策金融公庫などの政府系金融機関も事業者向けの融資を行っています。ただし、融資を受ければ当然利息が発生するため、無計画な借り入れは事態を悪化させかねません。
また株式発行によって、資本を増加させる方法もあります。弁済の必要がないのは大きなメリットですが、経営権が他者に移る可能性がある点を認識しておきましょう。
何らかの資産を保有している場合は、それを売却するのも一つの方法です。不動産を保有していない場合は、売掛債権を売却することでスピーディに現金化できるファクタリングを利用するのもよいでしょう。最短即日で資金調達できる可能性がある他、赤字の場合や税金を滞納している場合でも利用できるケースもあります。
まとめ
資金繰りの悪化は。最悪の場合、企業の倒産につながってしまいます。資金繰りは売り上げが減少したときはもちろん、増加したときに悪化するケースもあるため、業績が好調でも油断はできません。
資金繰りを改善するには、抜本的な事業改善の他、資金繰り表の作成や経費削減、資金調達などを検討しましょう。なお、資金調達にはさまざまな手段がありますが、中でもファクタリングは赤字や債務超過に陥っていても利用できるケースが多いです。
ファクタリング会社をお探しなら、株式会社Mentor Capitalがおすすめです。取引実績は年間3,000件以上で、審査通過率は92%と高い実績を誇ります(※)。お申し込みは24時間365日受け付けているので、お気軽にご相談ください。