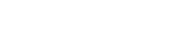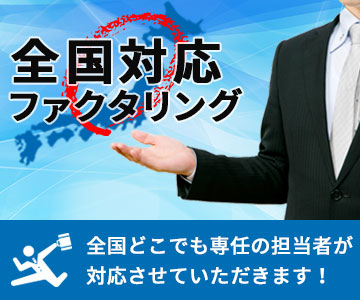リバースファクタリングとは? 通常のファクタリングとの違いやメリット・デメリットを解説
最終更新日:2025年04月30日
リバースファクタリングは、発注企業が買掛金をファクタリング会社に一時的に立て替えてもらうサービスです。発注企業がファクタリング会社と契約するサービスであり、外注先企業が売掛金を売却する通常のファクタリングとは別物です。
発注企業から見たリバースファクタリングのメリットは、支払いを先延ばしにして資金繰りを改善できることです。一方、外注先企業はファクタリング会社が立て替えてくれた代金を早期に受け取れます。
この記事では、リバースファクタリングの仕組みや通常のファクタリングとの違い、発注企業と外注先企業それぞれから見たメリット・デメリットを解説します。
Table of Contents
リバースファクタリングとは?
リバースファクタリングは、発注企業(代金を支払う側)が未払いの代金(買掛金)をファクタリング会社に立て替えてもらうサービスです。ファクタリング会社は外注先企業(代金を受け取る側)に対して代金を立て替えて支払い、その後、発注企業から代金を回収します。
通常のファクタリングは、外注先企業が売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらうのに対して、リバースファクタリングは買掛金がある発注企業が立て替えをしてもらう仕組みであり、両者は全くの別物です。
発注企業から見たリバースファクタリング導入のメリットとして、支払いを遅らせることで資金繰りを改善できることが挙げられます。企業の資金繰りを改善させる原則は「代金回収は早く、代金支払いは遅く」です。リバースファクタリングを導入して支払いを遅らせれば、手元の資金に余裕ができます。
一方、外注先企業から見た場合は、貸し倒れを回避できる、当初の想定通りに代金を回収できるなどのメリットがあります。
リバースファクタリングの仕組み
リバースファクタリングには、発注企業と外注先企業、ファクタリング会社の3社が関わります。
まず、発注企業が掛取引を行います。掛取引とは、商品やサービスを先に受け取り後で代金を支払う、いわゆるツケ払いの仕組みです。発注企業が後で支払うお金を買掛金、外注先企業が受け取るお金を売掛金といいます。
次に、発注企業はファクタリング会社にリバースファクタリングの利用申し込みを行います。ただし、全てのファクタリング会社がリバースファクタリングを取り扱っているわけではありません。また対応している場合でも、ファクタリング会社ごとに手数料や対応可能金額は異なります。
ファクタリング会社は、発注企業から提出された書類などを基に審査を行います。審査では、主に発注企業の支払い能力が問われます。一方、外注先企業の経営状態などは通常問われません。審査に合格した場合、発注企業は外注先企業の了承を得た上でファクタリング会社と契約内容を話し合います。具体的には、以下のような点を取り決めます。
・取り扱える買掛金の額
・立て替えの期日
・支払手数料
・支払期間
契約成立後、ファクタリング会社は外注先企業に対して代金を支払います。この際に支払われるのは、買掛金から手数料を引いた金額です。その後、発注企業がファクタリング会社に立て替えてもらった分の支払いを行えば、リバースファクタリングは完了です。
大まかな流れは以上となりますが、ファクタリング会社によっては細部が異なることもあります。契約する前に、具体的な流れを確認しておきましょう。
リバースファクタリングと通常のファクタリングの違い
リバースファクタリングと通常のファクタリングを比較すると、以下のようになります。
| – | リバースファクタリング | 通常のファクタリング |
| 利用主体 | 発注企業 | 外注先企業 |
| ファクタリングの対象 | 買掛金(買掛債務) | 売掛金(売掛債権) |
| 利用目的 | 発注企業が支払いを先延ばしにする | 外注先企業が早期に資金調達する |
| 手数料負担者 | 外注先企業 | 外注先企業 |
| 審査対象 | 発注企業(利用主体) | 発注企業(利用主体ではない) |
| 契約形態 | 3社間 | 2社間、もしくは3社間 |
リバースファクタリングと通常のファクタリングの大きな違いとして、利用主体と利用目的が挙げられます。リバースファクタリングは、発注企業が支払いを先延ばしにして、資金繰りを改善するための手段です。一方、通常のファクタリングは、外注先企業が売掛金を早期に現金化するための手段です。ただし、リバースファクタリングでは立て替えが行われるため、結果的に外注先企業が早期に資金を調達できる一面があります。
またリバースファクタリングでは、利用主体が審査対象となります。リバースファクタリングの実態は立て替えであり、すなわち利用主体に対する融資と近しい側面を持つためです。
一方、通常のファクタリングでは、利用主体ではなく売掛先である発注企業が主な審査対象となります。通常のファクタリングは売掛金を売買する仕組みであるため、利用主体の支払い能力はそこまで問われません。
またリバースファクタリングは発注企業が主体となって行いますが、外注先企業の許可が必要になります。一方、通常のファクタリングは外注先企業が主体となって行いますが、必ずしも発注企業の同意を得る必要はありません。
発注先の同意なしで行うファクタリングが2社間ファクタリングです。一方、発注先の同意を得て行うファクタリングが3社間ファクタリングです。2社間ファクタリングは審査スピードが早く、また発注企業にファクタリングの利用を知られずに済むメリットがあります。一方で、手数料が高くなりやすいというデメリットもあります。
なお、手数料はリバースファクタリング・通常のファクタリングどちらの場合も外注先企業が負担します。リバースファクタリングは発注企業が利用主体であるにもかかわらず、外注先企業に金銭的な負担が生じるため、場合によっては断られることもあるでしょう。
リバースファクタリングのメリット
ここでは、リバースファクタリングの主なメリットを解説します。リバースファクタリングは発注企業と外注先企業双方にメリットがあるため、それぞれの立場から見たメリットを別々に解説します。
発注企業にとってのメリット
発注企業がリバースファクタリングを導入する主なメリットは以下の4点です。
・支払いサイトが実質的に延長され資金繰りが改善する
・支払先を一本化できる
・優良な外注先との関係強化につながる
・下請法を遵守しながら支払いを先延ばしできる
支払サイトが実質的に延長され資金繰りが改善する
リバースファクタリングを利用すると、実質的に支払いサイトを延ばせます。支払いサイトとは、取引の締め日から実際に代金を支払うまでの猶予期間です。掛取引や手形取引を行う際には通常、支払いサイトが設定されます。
支払いサイトの中でも特にメジャーなのが「30日サイト(月末締め、翌月末払い)」です。例えば、発注企業が1月中に購入した商品やサービスの代金は、2月末にまとめて支払います。また「60日サイト(月末締め、翌翌月末払い)」もよく見られます。
商品の買い手である発注企業から見た場合、支払いサイトは長いに越したことはありません。支払いサイトが長ければ資金繰りに余裕が生まれ、急な出費や企業を成長させるための投資に手元資金を残しておけるからです。
リバースファクタリングを利用すれば、買掛金の支払いサイトを実質的に長くできます。手元資金に余裕はないけれど、外注先企業に支払いを待ってもらうのが難しい場合は、リバースファクタリングの利用を提案すると良いかもしれません。
支払先を一本化できる
多数の企業と取引を行っていて、支払業務にかかる手間やコストが無視できないくらい大きくなっている場合、リバースファクタリングを導入すれば支払業務を効率化できる可能性があります。
リバースファクタリングを利用しない場合、あらかじめ各外注先企業と買掛金の支払い方法や支払時期について同意した上で、複数社に支払いを行わなければなりません。外注先が数社程度ならば大した手間にもならないでしょうが、数十社ともなると相応の時間とコストがかかります。
このような場合、複数の外注先とリバースファクタリングの導入で同意できれば、請求書の管理や支払の手続きを一本化できます。それぞれの外注先に支払うのではなく、ファクタリング会社にまとめて支払うようになるため、支払業務の効率化が可能です。その結果、余ったリソースを他の業務に回したり、設備投資したりできるようになるかもしれません。
優良な外注先との関係強化につながる
リバースファクタリングを利用すれば、優良な外注先を確保しやすくなります。
外注先企業からすれば、回収サイト(締め日から代金回収までの期間)は短い方が好都合です。売掛金を早く回収できれば資金繰りに余裕ができますし、回収不能に陥るリスクも抑えられるからです。逆に、回収サイトが長い発注企業との取引にはどうしても消極的にならざるを得ません。
リバースファクタリングを導入すれば、外注先はファクタリング会社から早期に支払いを受け取れるようになるため、安心して契約を結べます。その結果、発注企業が優良な外注先と出会える可能性も高まります。
下請法を遵守しながら支払いを先延ばしできる
下請法とは、親事業者(発注企業)と下請事業者(外注先企業)の取引を公正なものとし、下請事業者の利益を保護するための法律です。正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。下請法では親事業者に対して「4つの義務」と「11の禁止事項」が定められており、違反した場合は公正取引員会から勧告が行われます。
そして11の禁止事項の中に「下請代金の支払遅延の禁止」があります。これは発注した物品などの納品日から60日以内で定める支払日までに代金を払わないことを禁止するものです。社内検査が済んでいないなどの発注企業の都合は、支払を引き伸ばす理由にはなりません。
リバースファクタリングを利用すれば、発注企業側の事情で60日以内に買掛金を支払えない場合でも、ファクタリング会社に一時的に立て替えてもらえます。そのため、下請法に対応しつつ、支払いを遅らせることが可能です。
※参考:公正取引委員会ガイドブック.「下請代金支払遅延等防止法ガイドブック」.
外注先企業にとってのメリット
リバースファクタリングは発注先企業だけでなく、外注先企業にもさまざまなメリットをもたらします。主なメリットは以下の2点です。
・早期に資金を確保できる
・貸し倒れリスクの軽減
早期に資金を確保できる
発注企業がリバースファクタリングを導入した場合、外注先企業は売掛金を早期に回収できます。具体的にいつ代金が支払われるかは一概にはいえませんが、場合によっては請求書を発行してすぐに売掛金を現金化できます。
売掛金を早期に回収できれば、資金繰りに余裕ができるでしょう。その資金を元手に、事業の安定化や新規事業の拡大に取り組めるかもしれません。
なお、発注企業がリバースファクタリングを導入していない場合は、通常のファクタリングによって早期に現金化が可能です。通常のファクタリングは売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらうサービスであり、2社間ファクタリングならば発注企業の同意は不要です。
貸し倒れリスクを軽減できる
発注企業がリバースファクタリングを導入した場合、貸し倒れのリスクが低くなります。
貸し倒れとは、発注先の資金繰り悪化や倒産などによって売掛金などの金銭債権が回収できなくなることです。通常、支払遅延が発生した場合にはまずは電話やメールなどで催促を行います。それでもなお支払いが行われなければ交渉、あるいは法的手段などを経て債権を回収します。手間も時間もかかりますし、そもそも回収できるとも限らないため、貸し倒れはできる限り避けなければなりません。
リバースファクタリングを導入してもらえれば、ファクタリング会社から立て替えを受けられるため、貸し倒れリスクが低くなります。仮に立て替えを受けた後で発注企業が倒産しても、それはファクタリング会社と発注企業の問題であり、外注先企業にはデメリットはありません。
リバースファクタリングのデメリット
上記の通り、リバースファクタリングは発注企業と外注先企業の双方に大きなメリットをもたらす一方で、無視できないデメリットもあります。
発注企業にとってのデメリット
発注企業がリバースファクタリングを導入する主なデメリットは以下の4点です。
電子記録債権(でんさい)の導入が必要
リバースファクタリングを取り扱う業者が少ない
自社が審査の対象となる
外注先企業の同意が必要
電子記録債権(でんさい)の導入が必要
リバースファクタリングを導入する場合、発注企業は電子記録債権(でんさい)を導入しなければなりません。
電子記録債権は、既存の小切手や手形に代わる新しい決済手段です。紙の小切手や手形とくらべて紛失・盗難・偽造などのリスクが低く、取引の透明性を向上させられるというメリットがあります。
電子記録債権は「電子債権記録機関」が管理しています。2025年3月20日現在、日本に存在する電子債権記録機関は以下の5社です。
日本電子債権機構株式会社
SMC電子債権記録株式会社
みずほ電子債権記録株式会社
株式会社全銀電子債権ネットワーク
TranzaX電子債権株式会社
上記の機関の中で、もっとも加盟金融機関が多いのが株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)です。でんさいネット上で取り扱われる電子記録債権をでんさいといいます。ここでは、でんさいネットの利用を前提に話を進めます。
でんさいネットを利用する際には、でんさいネットに加盟している取引金融機関と利用契約を結ぶ必要があります。でんさいネットと直接契約するわけではありません。利用料金は金融機関によって異なりますが、三井住友銀行の場合1件ごとに税込440円(受取人口座が他行なら税込770円)の発生記録手数料がかかります(2025年3月20日時点)。
電子記録債権は便利なサービスですが、自社と外注先企業の双方が導入していなければ利用できません。外注先企業がまだ導入していない場合は、切り替えの案内状を送りましょう。また導入前に、権限者の設定や社内事務・会計システムの整備も行っておきましょう。
※参考:三井住友銀行.「SMBCでんさいネット ご利用料金」
リバースファクタリングを取り扱う業者が少ない
通常のファクタリングを取り扱うファクタリング会社が多数あるのに対して、リバースファクタリングを取り扱う業者は現状ごく少数です。Mentor Capitalでも取り扱いはありません。複数の業者を比較できればベストですが、現状なかなか難しい一面もあります。
自社が審査の対象となる
通常のファクタリングでは自社ではなく売掛先企業が主な審査対象になりますが、リバースファクタリングでは自社が審査の対象となります。
リバースファクタリングを取り扱っている業者が非常に少なく、またファクタリング会社ごとに方針の違いもあるため、審査基準は不明瞭な点が多いです。ただし、リバースファクタリングは融資と似たような側面を持つため、通常の銀行融資などと同じように支払い能力が問われることは間違いありません。
例えば、決算書が赤字続きである場合は、審査に通る可能性が極端に低くなります。また、債務超過(保有する資産の総額よりも負債の総額が大きい)に陥っている場合も、審査に通る可能性は低くなるでしょう。その他、金融事故歴や税金・公共料金の滞納なども審査に通らない原因になります。
外注先企業の同意が必要
リバースファクタリングを導入する場合、発注企業は外注先企業から同意を得なければなりません。
外注先企業は自社の財務状況や資金繰りなどを基に、リバースファクタリングを導入するかどうかを決めます。先述の通り、手数料を払うのは外注先企業であるため、場合によっては断られることもあるでしょう。特に契約金額が多額の場合、その分手数料も高くなるため、断られるリスクは高くなります。
では外注先の同意が得られない場合、発注企業はどうすべきでしょうか。資金に余裕がある場合は、手数料の一部もしくは全部を契約金額に上乗せしても良いでしょう。リバースファクタリングは手数料がかかることを除けば外注先企業にとっても大きなメリットのある仕組みですので、受け入れられる可能性が高まります。それでもなお、同意が得られない場合は、他の方法で支払いサイトを伸ばしましょう。
外注先企業にとってのデメリット
外注先企業がリバースファクタリングの導入によって受ける主なデメリットは以下の3点です。
・電子記録債権(でんさい)の導入が必要
・手数料の負担
・発注企業への依存
電子記録債権(でんさい)の導入が必要
リバースファクタリングを導入する場合、外注先企業も電子記録債権(でんさい)を導入しなければなりません。前述の通り、電子記録債権は新しい決済手段の一つです。
リバースファクタリングを導入したいと考えている発注企業から電子記録債権導入の案内状が送られてきたら、まずは導入することによるコスト面でのメリット・デメリットを試算してみましょう。
電子記録債権を導入すれば、手形代、印紙税、郵送料などの他、手形の発行や管理などにかかっていた人件費を大幅にカットできます。一方で、決済手数料や分割譲渡記録手数料など、電子記録債権ならではのコストも発生します。また、前述の通りリバースファクタリングの手数料は外注先企業が負担することにも留意が必要です。
それでもトータルで考えればメリットの方が大きくなることが多いですが、企業の規模によってはデメリットが大きくなるかもしれません。
メリットが十分大きいと考えられる場合は、取引金融機関と契約を行い、取引先に回答書を返送しましょう。また、電子記録債権を取り扱う事務・会計システムの整備も忘れずに行ってください。
手数料の負担
前述の通り、リバースファクタリングの手数料は外注先企業が負担します。手数料の相場は買掛金の5~10%程度です。ただし、手数料は同じファクタリング会社なら常に一定になるわけではなく、買掛金の額面や支払いサイトによって変動します。基本的に、支払いサイトが長いほど回収不可能になるリスクが高まるため、手数料も高くなります。建設業など特定の業種は支払いサイトが長くなりやすいため注意が必要です。
問題は5~10%の手数料をどう見るかですが、迅速に資金を用意できる手段としては悪くない数字だといえます。
例えば、銀行や日本政策金融公庫の融資はリバースファクタリングの手数料よりも低い貸付金利が採用されることが多いです。しかし、融資は審査が厳しく、また時間がかかるというデメリットがあります。
一方、リバースファクタリングでは審査を受けるのは発注企業ですので、自社の経営状態に問題があっても利用できるケースが多々あります。回収サイトも短くできますし、手数料分の価値を見出せることも多いでしょう。
発注企業への依存
リバースファクタリングは外注先企業にとっても便利なシステムですが、それゆえに発注企業に過度に依存してしまいやすい一面もあります。
回収サイトを短くするために、リバースファクタリングを導入している特定の企業とばかり取引をするのは、リスクの高い行為です。発注企業の経営がうまくいっているときは良いですが、仮に発注企業が倒産してしまった場合、大口の取引先を失うことになり、売上が一気に低下してしまいます。また、発注先の海外移転や仕入方針の転換の影響も大きく受けることになります。
また、発注企業に依存していることが発注企業側に伝わった場合、価格交渉で足元を見られるかもしれません。契約を続けてもらうことを優先し過ぎれば値下げ圧に抗えず、新たな商品の開発や新規顧客の開拓がおろそかになってしまうことも考えられます。
もちろん、取引先を集中させればスケールメリットを享受できる、経理や営業担当者の負担を減らせるなどのメリットもあります。ただ、ごく少数の発注先に過度の依存をするのが大きなリスクであることには変わりありません。取引先はある程度意図的に分散させた方が良いでしょう。
まとめ
リバースファクタリングは、発注企業が買掛金をファクタリング会社に一時的に立て替えてもらえるサービスです。ファクタリング会社は外注先企業に対して支払いを行い、その後発注企業から代金を回収します。リバースファクタリングを利用する場合、発注企業と外注先企業、両者が電子記録債権を導入しなければなりません。
リバースファクタリングは発注企業と外注先企業、双方にメリットをもたらします。発注企業の主なメリットは、支払いサイトを延ばせることです。支払いサイトが伸びれば、それだけ日々の資金繰りに余裕ができます。一方、外注先企業にとっての主なメリットは、回収サイトを短縮できることです。早く資金を回収できれば、やはり資金繰りに余裕ができます。また売掛金の未回収リスクも減らせます。
ただし、現状リバースファクタリングを取り扱っているファクタリング会社は多くありません。そこで活用したいのが、通常のファクタリングです。
通常のファクタリングは、外注先企業がファクタリング会社に売掛金を買い取ってもらえるサービスです。売掛金を売却する仕組みであり、融資ではないので審査が比較的易しく、しかも短期間で現金を得られます。
Mentor Capitalも、通常のファクタリングサービスを行っています。最短即日の資金調達が可能で、審査通過率は約92%です。オンラインなら24時間365日いつでも無料査定を受け付けています。まずは一度ご相談ください。