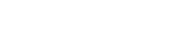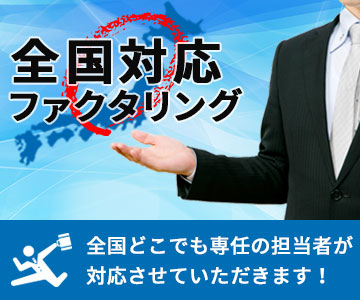無借金経営のデメリットとは? メリットや実質無借金経営についても解説
最終更新日:2025年09月10日
企業経営において借金をしないことは、一見すると健全で理想的に思えるかもしれません。しかし、無借金経営には資金管理や倒産リスク軽減などのメリットがある一方で、融資を受けにくくなったり、事業拡大の機会を逃したりするデメリットも存在します。さらに経営状況や業種によっては、あえて借り入れをする実質無借金経営を目指した方が安定的な成長につながる場合もあるのです。
そこで本記事では、無借金経営と実質無借金経営それぞれの概要やメリット・デメリット、実質無借金経営を実現するためのポイントなどについて解説します。
Table of Contents
無借金経営とは?
無借金経営とは、貸借対照表に有利子負債が一切ない状態で行われる経営のことです。
負債とはいわゆる借金で、利息が発生する有利子負債と利息が発生しない無利子負債に分けられます。具体的には、有利子負債とは銀行や信用金庫からの融資や、資金調達のために発行する社債などのことです。
一方、無利子負債とは買掛金や未払費用、支払手形などのことです。無利子負債があっても、有利子負債がなければ無借金経営が達成できているといえます。
無借金企業の割合
東京商工リサーチの調査によれば、2022年の全国の無借金経営企業は6万6,370社で、無借金率は21.6%でした(※)。2019年の24.4%から減少しているものの、およそ5社に1社が無借金経営を達成していることになります。
地域別に見た場合、無借金率の割合が最も高いのは九州の24.83%でした。次いで四国の22.79%、中国の22.58%、関東の22.08%、北陸の21.59%、近畿の20.93%、北海道の20.14%、東北の19.43%と続いています。最下位は中部の19.23%でした。
産業別に見た場合、サービス業などの無借金率は47.08%、金融・保険業でも40.24%と高い一方、製造業は12.00%にとどまっていました。
※参考:東京商工リサーチ.「「無借金」企業率は21.6%、コロナ前より2.8P下落 コロナ支援のゼロ・ゼロ融資などの活用でダウン」.
無借金経営と自己資本率100%の違い
無借金経営と類似した概念に、自己資本率100%があります。両者の違いは、事業負債(≒無利子負債)があるかどうかです。事業負債とは、仕入債務(支払手形、買掛金など)、未払給与などのことです。有利子負債がなくても事業負債がある場合は無借金経営で、両方ともなければ自己資本率100%といえます。
| 有利子負債 | 事業負債(≒無利子負債) | |
| 無借金経営 | ない | ある |
| 自己資本率100% | ない | ない |
多くの企業は仕入れの際に買掛金や支払手形の仕組みを利用している他、人を雇っていれば未払給与も発生します。そのため事業負債の仕組みを一切利用せずに企業経営を行うのは難しく、自己資本率100%を維持している企業は少ないといえるでしょう。
無借金経営のデメリット
無借金経営は、借金して行う経営よりも健全に見えます。しかし、実は無借金ならではのデメリットもあります。ここからは主なデメリットについて見ていきましょう。
銀行からの融資を受けにくい
無借金経営のデメリットとして、銀行からの融資が受けにくいことが挙げられます。銀行などの金融機関は一般的に、過去の取引実績を重視します。簡単にいえば、過去に借り入れをして滞りなく完済した実績がある企業を高く評価するのです。一方で無借金経営を続けている企業にはその実績がないため、どうしても銀行からの評価が低くなりがちです。
また銀行側からすると、入念な審査が必要な新規顧客よりも、昔から付き合いのある企業を優先した方が効率的に利息収入が得られます。無借金経営を続けると、財務状況に特に問題がなくても、融資が後回しにされてしまうかもしれません。
さらに銀行の審査では、自己資本の割合も重視されます。無借金経営を行っている企業は自己資本が乏しいケースも多く、その場合財務基盤が脆弱だと見なされやすいです。
「無借金経営を続ける予定で、銀行からの融資が受けづらくても問題ない」と考えるかもしれませんが、今後も経営が順調に続く保証は全くありません。突然の不景気や市場の変化、災害、社員の大量離職などで経営が急激に悪化するリスクは常に存在します。そのようなときに、銀行からの融資が受けられないのはデメリットといえるでしょう。
資金がショートする可能性がある
資金ショートとは、手元の資金が不足して直近の支払いができなくなることです。負債が資産を上回る「債務超過」や、損失が発生している「赤字」とは異なります。
無借金経営を続けていても、手元に現金がなければ資金がショートしてしまいます。例えば大量の売掛債権があっても、回収前に買掛金や給料の支払いがあり、かつ手元に現金がない場合は資金ショートとなり、事業を続けるのが困難になるでしょう。無借金経営にこだわり過ぎるがあまり、手元の資金を枯渇させないように注意が必要です。
雇用できなくなる
無借金経営にこだわり過ぎると、優秀な人材を確保できなくなるかもしれません。株式会リクルート就職みらい研究所の「就職白書2020」によれば、2019年度の1人当たりの採用単価は新卒で93.6万円、中途で103.3万円でした(※)。
手元の資金が多い大企業ならばともかく、中小企業がこれだけの費用を無借金で用意するのは大変です。無借金での採用にこだわり過ぎた結果、優秀な人材を逃してしまい、得られる利益が減ってしまっては本末転倒でしょう。
※参考:株式会社リクルート 就職みらい研究所.「就職白書2020」.
事業規模を拡大しにくい
無借金経営にこだわり過ぎると、事業規模拡大のチャンスを逃してしまうかもしれません。ある程度の借金をして手元資金の余裕を作っていれば、急な大量注文にも対応しやすくなりますが、無借金経営に固執すると急な大量注文にも柔軟に対応できません。めまぐるしく市場が変化する現代で、こうした千載一遇のチャンスを逃すのは企業にとって大きな損失となるでしょう。
無借金経営のメリット
無借金経営にはデメリットもある一方で、メリットももちろんあります。ここでは主なメリットをご紹介します。
資金管理が楽になる
無借金経営の大きなメリットとして、資金管理が楽なことが挙げられます。有利子負債がないため、完済までの資金計画を立てる必要がありません。借入金額や利息、完済時期の把握などをすることもなくなります。また、支払いが遅れてしまい、融資やクレジットカードに関する信用情報に傷が付いてしまった、ということもないでしょう。
特に中小企業やスタートアップ企業は、人材や資金などの経営資源に余裕がないことも多いです。無借金経営であれば、煩わしい資金管理に時間を取られずに済みます。
利息を支払う必要がない
無借金経営ならば、利息の支払い義務は生まれません。借り入れがなければ成長スピードが遅くなる可能性はあるものの、無計画な借り入れによる利息の支払いによって経営悪化につながるリスクがなくなります。
決算書の見栄えが良くなる
無借金経営を行うと、決算書の見栄えが良くなりやすいです。企業の決算書にはいくつかの種類がありますが、無借金経営では特に貸借対照表の見栄えを良くできます。貸借対照表は、企業が保有する資産や負債、純資産のバランスをまとめたものです。表の左側に資産、右側に負債と純資産が記載されており、左右の金額は常に一致します。
無借金経営企業の貸借対照表には、有利子負債がありません。その分負債の部の割合が小さくなり、自己資本比率(資産に対する純資産の割合)が相対的に高くなります。自己資本比率が高い企業は財務的に安定していると評価されやすく、金融機関や投資家からの信用も得やすくなりやすいです。「将来融資を受けたい」、「企業を売却したい」と考えている場合、自己資本比率をある程度高めておいた方がよいでしょう。
自由に意思決定できる
無借金経営は、企業の意思決定の自由度を高めます。融資によって、銀行などの金融機関と良好な関係を持つことで利点がある一方で、金融機関の意向に経営が影響されてしまうケースもあるでしょう。必要のない融資を勧められて受けてしまい、その後の利息負担に苦しむケースもあります。無借金経営ならばそもそも銀行と頻繁にやり取りする必要がないため、第三者に深く介入されることのない自由な意思決定が可能です。
ただし、無借金経営であっても株主やベンチャーキャピタルなどから出資を受けている場合は、その意向が経営に影響する可能性があります。
倒産リスクを軽減できる
無借金経営は、倒産リスクを軽減できる可能性があります。東京商工リサーチの調査によれば、無借金企業は黒字の割合が77.0%で、赤字は22.9%でした(※)。全国の普通法人の赤字法人率が66.6%であることを踏まえると、無借金企業は赤字の割合が少ないといえるでしょう。
ただし、先述した通り、無借金経営は資金ショートのリスクを高める一面もあります。借入金が支払えなくなることによる倒産リスクは抑えられる一方で、運転資金が不足して事業継続が困難になる恐れがあることを認識しておきましょう。そのため、無借金経営は全ての状況で適切であるとは限らず、資金計画や事業の特性に応じた判断が重要です。
※参考:東京商工リサーチ.「全国の「無借金企業」8万4,000社調査」.
実質無借金経営を目指すのがおすすめ
無借金経営にはメリットも多い一方で、デメリットもあります。企業の状況によっては、借入をしないことが適切だとは限りません。必要なときに資金を借りられる体制を整えつつ、有利子負債をできるだけ少なく抑える「実質無借金経営」を目指すことがおすすめです。
実質無借金経営とは?
実質無借金経営とは、有利子負債があるものの、それを完済しようと思えばいつでもできる状態に保つことです。例えば、500万円の有利子負債があっても、手元資金(現金や預金、短期の有価証券など)が1,000万円あればいつでも完済できます。この状態が実質無借金経営です。また有利子負債を完済しても、経営に必要な運転資金が残る程度には手元資金を確保しておくようにしましょう。
なお、内閣府によると、日本において実質無借金経営を行っている企業の割合は増えてきています(※)。
実質無借金経営のメリット
実質無借金経営には、さまざまなメリットがあります。主なメリットを見ていきましょう。
金融機関との関係性を維持できる
実質無借金経営のメリットとして、金融機関との関係性を維持できる点が挙げられます。先述した通り、銀行などの金融機関は利用実績を重視します。実質無借金経営は無借金経営とは異なり、借り入れを行いながら経営する仕組みのため、金融機関との関係性を維持することが可能です。金融機関と十分な関係性を保っていれば、急に業績が悪化したり業界全体が不況に陥ったりした場合でも、優先的に融資を受けられる可能性が高まります。
もちろん、実質無借金経営では負債の利息を支払う必要がありますが、いざというときに優先的に助けてもらうための費用だと考えれば、必ずしも無駄とはいえません。無理に借り入れをする必要はありませんが、安易に金融機関との関係を断つのは望ましくないでしょう。
金融機関からコンサルティングを受けられる
金融機関と接点があれば、コンサルティングを受けることもできます。従来のように利息収入を中心とした収益モデルの維持が難しくなったことから、保有する豊富な顧客データや業界知識を活用し、コンサルティングサービスの拡充に力を入れ始める金融機関が増加傾向にあります。
具体的なサービス内容は金融機関ごとに異なりますが、場合によっては新たな取引先を紹介してもらえたり、経営状態の相談に乗ってもらえたりするでしょう。
自己資本比率が高まる
自己資本比率とは、資産に対する純資産の割合です。例えば、資産が1,000万円、負債が600万円、純資産が400万円の場合、自己資本比率は400万円÷1,000万円=40%となります。自己資本比率は会社の財務的な安定性を示し、比率が高いほど経営の安定度が高いと評価されることが一般的です。
実質無借金経営では多くの負債を抱えることは少ないため、自己資本比率は高くなります。自己資本比率が高い状態を維持しておけば、短期間の内に経営破綻するリスクを小さくできる上に、融資の審査でも有利に働きやすいです。
法人税が安くなる
実質無借金経営は、法人税対策にもなります。法人税の計算式は「課税所得×法人税率」で表されます。課税所得は税法上の益金から損金を引いた額であり、収益から費用を引いた額とは厳密には異なりますが、重なる部分も多いです。
金融機関に支払う利息は、原則として損金に算入できるため、借り入れをしている場合は課税所得を減らす効果があります。なお、課税所得が減れば法人税も減りますが、減額分は支払利息の一部にとどまり、全額を相殺できるわけではないことを認識しておきましょう。
実質無借金経営のデメリット
実質無借金経営には、デメリットもあります。詳細について見ていきましょう。
ある程度の資金を確保しておく必要がある
実質無借金経営を達成するためには、ある程度のまとまった資金を確保しておかなければなりません。具体的には、有利子負債額以上の手元資金が必要です。例えば、有利子負債が500万円ある場合、最低でも500万円分の資金を確保しておく必要があります。なお、実際には500万円ぴったりやそれに近い額では、リスクへの備えとしては不十分です。予期せぬ事態にも対応できるよう、ある程度の余裕を持って資金を確保しておく必要があります。
自由に廃業できなくなる
実質無借金経営の企業が、自由なタイミングで廃業するのは難しいです。実質無借金経営といえども有利子負債を抱えていることには変わりないため、原則として廃業前に弁済しなければなりません。もちろん、完済すれば廃業できるようになります。
廃業を考えている場合は、スムーズに事業を辞められるように支払いの計画を立てておくとよいでしょう。
実質無借金経営を実現するためのポイント
ここからは、実質無借金経営を実現するために押さえておきたいポイントをいくつかご紹介します。
運転資金を確保しておく
実質無借金経営を実現するためには、運転資金の確保は非常に重要です。企業の経営にはお金がかかります。万が一、有利子負債を完済した直後に急に売り上げが減少しても耐えられるように、しばらくは各種経費を支払えるだけの手元資金を残しておかなければなりません。
手元資金をいくら用意しておくべきかは業種や企業規模によって異なりますが、有利子負債を完済した後でも、月商の最低3カ月分は確保しておくのがよいでしょう。例えば、有利子負債が500万円あり、月商が300万円の場合は「500万円+(300万円×3カ月)=1,400万円」が目安となります。1,400万円よりも多ければさらに経営は安定しやすいですが、資金を手元に抱え過ぎていても十分な投資や事業拡大ができず、企業の成長スピードを鈍らせるリスクとなり得るので注意しましょう。
金利を見極める
実質無借金経営はあえて少額の有利子負債を持ち、利息を支払うことで金融機関とのつながりを維持する方法ともいえます。利息負担のデメリットが大き過ぎる場合は、有利子負債を完済して無借金経営に切り替えた方がよいかもしれません。銀行融資などの金利はそれほど高くないものの、市況の変化によって利息負担が重くなる可能性もあります。その場合は、早めに支払いを済ませた方がよいでしょう。
自社の状況を見極める
実質無借金経営は多くの企業にメリットがありますが、全ての企業が目指すべきとは限りません。業種や経営状況によっては、手元資金以上の融資を活用して事業拡大を図った方が有利なケースもあります。
特に起業の直前・直後は何かと経費がかかりやすい上に売り上げは少ないことが多いです。こうした状況で実質無借金経営にこだわると、成長の機会を逃しかねません。スタートアップ時は積極的に融資を受けて事業を拡大し、経営が安定してきたら実質無借金経営に切り替えるなどの柔軟な対応が求められます。
自社の状況に合った融資先を選ぶ
金融機関によって、金利や審査スピード、審査の通りやすさといった借り入れの条件は異なります。例えば、すぐに資金が必要な場合は審査スピードが早い金融機関を選ぶのがよい一方で、特に急いでいない場合は審査に時間がかかっても金利の低い金融機関を選んだ方がよいでしょう。自社の状況に合った融資先を選ぶことが大切です。
ここからは、銀行・信用金庫やノンバンクの概要をご紹介します。
銀行・信用金庫
銀行や信用金庫からの借り入れは、企業が利用できる融資の中でも特にメジャーなものです。銀行と信用金庫の主な違いは、以下の通りです。
・銀行:株式会社で、中小企業から大企業まで幅広い顧客層に対応している
・信用金庫:非営利法人で、主な顧客は地域の中小企業や個人
さらに銀行融資は他の資金調達手段と比べて金利が低く、借入限度額は大きく設定されることが多いです。反面、審査は厳しく、中小企業やベンチャー企業は融資自体を断られることも珍しくありません。また審査にかかる時間も長いです。
信用金庫は地域に密着したサービスを展開しており、中小企業やベンチャー企業でも比較的融資を受けやすいです。もちろん誰でも借りられるわけではなく、審査を通過する必要があります。ただし、金利は銀行と比べてやや高く、融資限度が低くなりやすいため、大規模な借り入れには向いていないでしょう。
ノンバンク
ノンバンクとは、預金業務を行わない金融機関の総称です。顧客からお金を預かることはせず、お金を貸し出す与信業務に特化しています。代表例はクレジットカード会社や消費者金融などです。ノンバンクも銀行と同様に、法人向けの融資を行っています。
ノンバンクのメリットとして、銀行や信用金庫と比べると審査基準が低いことが挙げられます。もちろんどのような企業でも借りられるわけではありませんが、銀行や信用金庫に融資を断られた際には、ノンバンクからの借り入れが有力な選択肢となるでしょう。業者によっては即日で融資を受けられることもあります。
一方で、ノンバンクの金利は銀行や信用金庫と比べると高めです。審査基準が低い傾向にあるため貸し倒れも発生しやすく、それを補うために金利が高めに設定されています。金利が高い分、支払い計画はより入念に立てる必要があります。
また、ノンバンクを名乗る業者の中に悪徳業者が混ざっている可能性も否定できません。利用前に貸金業の登録をしているか必ず確認しましょう。
資金調達の方法としてファクタリングを検討するのも一つの方法
融資には該当しませんが、資金調達の方法の一つであるファクタリングについても見ていきましょう。ファクタリングとは、売掛債権を支払期日よりも前にファクタリング会社に買い取ってもらう資金調達方法です。手数料が発生する代わりに、通常よりも早く現金を入手できるのが特徴です。
ファクタリングには売掛先の承諾が不要な2社間ファクタリングと、承諾が必要な3社間ファクタリングがあります。2社間ファクタリングの場合、売掛先の承諾が不要なため迅速に資金を調達できるものの、手数料は高めです。3社間ファクタリングは売掛先の承諾が必要なため時間がかかりますが、手数料を抑えられます。
ファクタリングのメリットは、融資と比べて審査が易しいことです。ファクタリングはあくまでも売掛債権の売却であるため、自社の経営状態に問題があっても売掛債権の回収不能リスクが低ければ審査に通る可能性が高いです。また融資ではないので信用情報にも影響が出ません。
一方、デメリットとしては手数料が高い傾向にあることが挙げられます。特に2社間ファクタリングはその傾向が強いため、安易な利用は避けましょう。またファクタリング会社を装って、融資を受けさせようとしてくる悪徳業者も存在するため注意が必要です。悪徳業者かどうか見分ける際には、以下の内容を確認しておきましょう。
・企業情報を開示しているか
・見積もりや契約書の内容が明確か
・手数料が相場よりも高過ぎたり低過ぎたりしていないか
・担当者の対応が丁寧か
まとめ
安定した経営を実現するためには、自社の状況に合った資金調達方法を選ぶことが大切です。売掛債権を多く抱えている場合は、融資の他にファクタリングの利用を検討するのもよいでしょう。ファクタリングは利息が発生せず、売掛債権を支払期日前に現金化できるというメリットがあります。
ファクタリング会社の中でもおすすめなのが、株式会社Mentor Capitalです。年間3,000件以上の豊富な取引実績があり、最短60秒の簡単審査と、審査通過率92%の柔軟な対応が特徴です。最短即日で資金を調達できるケースもあります。赤字・債務超過・個人事業・税金滞納などにも対応しているので、他社で断られた経験がある方もお気軽にご相談ください。