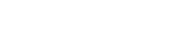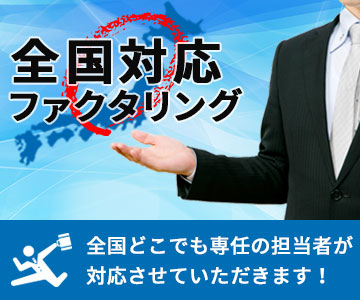未収金とは? 売掛金との違いや仕訳例、決済処理する際のポイントなどをご紹介
最終更新日:2025年09月26日
企業の経理担当者や経営者の方に向けて、未収金の仕組みを解説しています。未収金が発生する取引例や仕訳のやり方の他、売掛金や未収益金(未収収益)との違い、回収が遅れた場合の対策などもご紹介しています。
未収金は、企業が本業以外の取引で得た単発的な債権です。固定資産や有価証券を売却した場合に発生する未収金は金額が大きくなりやすいため、記帳漏れや金額の誤りは決算時の混乱につながります。適切な会計処理を心がけることが大切です。
また、未収金は売掛金同様に債権の一種であるため貸し倒れのリスクがあります。相手が支払いを行わない場合は、適切な手順で請求・回収しなければなりません。
本記事では未収金の仕組みや売掛金・未収益金(未収収益)との違い、仕訳例、未払いが続く場合の具体的な回収手順などを解説しています。未収金の扱いにお悩みの方はぜひ参考にしてください。
<この記事で分かること>
・未収金(未収入金)の概要・仕組み
・未収金・売掛金・未収益金それぞれの違い
・未収金の仕訳例
・未収金を決算処理する際のポイント
Table of Contents
未収金(未収入金)とは?
未収金(未収入金)とは、企業の主たる営業取引以外の反復性の薄い取引によって発生する債権(未回収の代金)のことです。例えば土地や建物、機械設備などを掛取引(代金後払い)で売却した場合、未収金が発生します。未収金と未収入金は基本的には同じ意味の言葉であり、会計や経理の場では「未収金」という表記が使われることが多いです。
なお、未収金は通常、流動資産として扱われます。流動資産とはおおむね1年以内に回収する債権のことです。未収金に限らず、資産の管理は財務状況を把握する上で重要なことなので、適切に行いましょう。
未収金・売掛金・未収益金は何が違うの?
未収金と類似した概念に、売掛金や未収益金(未収収益)があります。いずれも会社の立場から見た場合、原則として「近い将来入金される債権である」という点では同じですが、異なる点もあります。それぞれの主な違いについて見ていきましょう。
計上対象となる取引の違い
未収金・売掛金・未収益金(未収収益)は、対象とする取引が異なります。
まず、主たる営業取引によって生じた債権は、提供したものやサービスにかかわらず原則として売掛金に該当します。例えば、企業が自社製品を掛取引で販売した場合は売掛金が発生するため、そのように記帳しましょう。
一方、主たる営業取引以外の取引によって生じた債権は、未収金もしくは未収益金(未収収益)に該当します。どちらも本業以外の取引で生じた債権という点では同じですが、一時的な取引では未収金が、継続的な取引では未収益金(未収収益)が発生します。
例えば企業が保有していた建物や土地、機械設備などを売却した場合に発生する債権について考えてみましょう。これらの取引は通常反復して行わない一時的な取引であるため、発生する債権は未収金に該当します。
一方、貸金業者ではない企業が金銭を貸し付けた際の利息や、不動産会社でない企業が保有する不動産で得る賃料などは継続的に発生するため、債権は未収益金(未収収益)に該当します。
貸借対照表上の違い
貸借対照表は、企業が保有する資産、負債、純資産を表形式でまとめたものです。資産は流動資産、固定資産、繰延資産の3つに区分されます。
未収金は通常は流動資産です。ただし、回収が1年を超える場合は固定資産になります。
売掛金も通常は流動資産です。ただし、前の決算日で売掛金とした、本業以外の取引から発生する債権が1年経っても回収できていない場合は、固定資産である長期未収入金へと計上し直さなければなりません。長期未収金がある場合は、回収のための法的手段も視野に入れる必要があります。
未収益金(未収収益)も通常は流動資産です。
相手勘定の違い
相手勘定とは、ある勘定科目に注目した際に、仕訳の反対側に来る勘定項目のことです。例えば、現金による売上が発生した場合、仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現金 | 10,000 | 売上 | 10,000 |
この場合は「現金の相手勘定は売上である」「売上の相手勘定は現金である」といえます。
未収金の相手勘定は、資産と営業外損益(売却損益)です。営業外損益は、文字通り企業が本業の営業活動以外で得た損益のことを指します。
売掛金の相手勘定は、売上高です。売上高は企業が製品やサービスの販売で得た収入の総称です。企業にとっては利益の源泉であり、経営状態を示す指針でもあります。
未収益金(未収収益)の相手勘定は、営業外収益です。営業外収益とは、本業とは関係がなく、なおかつ継続的に発生する収益のことです。具体的には、受取家賃や受取利息が該当します。営業外損失という区分もありますが、未収益金(未収収益)の相手勘定になることは通常ありません。
未収金・売掛金・未収益金の具体例
ここからは、未収金・売掛金・未収益金(未収収益)の具体例を解説します。
先述した通り、未収金とは本業以外でなおかつ反復性がない取引を行った際に発生する債権のことです。例えば、事業のために所有していた固定資産の売却は通常単発で行われるため、未収金が発生します。
まず、帳簿価額が1,000万円の土地を1,200万円で売却した場合を考えてみましょう。この場合、相手勘定の資産は土地、特別損益は固定資産売却益になるため、仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未収金 | 12,000,000円 | 土地 | 10,000,000円 |
| 固定資産売却益 | 2,000,000円 |
次に、帳簿価額が1,000万円の土地を800万円で売却した場合を考えてみましょう。このケースでは固定資産売却損が発生するため、仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未収金 | 8,000,000円 | 土地 | 10,000,000円 |
| 固定資産売却損 | 2,000,000円 |
売掛金は、本業として商品やサービスを掛取引で販売した場合に発生します。例えば、50万円の商品を掛取引で売却した場合を考えてみましょう。この場合、相手勘定は売上になるため、仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 売掛金 | 500,000円 | 売上 | 500,000円 |
未収益金(未収収益)は、本業以外でなおかつ反復性がある取引を行った場合に発生します。例えば、預金の利息が3万円ある場合について考えてみましょう。この場合、相手勘定の営業外収益は受取利息となるため、仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未収収益 | 30,000円 | 受取利息 | 30,000円 |
未収金の仕訳例
ここでは、未収金が発生した場合のさらに具体的な仕訳の方法を解説します。
未収金が発生した場合
未収金が発生した場合、その時点で記帳を行います。なお、取引が発生した時点で記帳する考え方を発生主義といいます。例えば、帳簿価額が100万円の有価証券を120万円で売却した場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未収金 | 1,200,000円 | 有価証券 | 1,000,000円 |
| 有価証券売却益 | 200,000円 |
未収金が入金された場合
未収金が入金された場合も、速やかに仕訳を行いましょう。前述の未収金120万円を銀行振込で回収した際の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 1,200,000円 | 未収金 | 1,200,000円 |
このように、未収金がある場合は「発生時」と「回収時」の2回に分けて記帳を行います。回収時の記帳は忘れやすいため、注意しましょう。
本業以外の収益を得た場合
本業以外の活動で得た収入のうち、他の勘定科目に該当せず、なおかつ金額が比較的少ない収入を雑収入といいます。掛取引で雑収入を得た場合も、未収金として処理します。例えば、不用品を売却して5,000円の未収金が発生した場合の仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未収金 | 5,000円 | 雑収入 | 5,000円 |
その後、上記の未収金を銀行振込で回収した場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 5,000円 | 未収金 | 5,000円 |
なお、雑収入に該当する収入には、以下のようなものがあります。
・満期保険金、解約保険金
・損害賠償金
・助成金、補助金
・スクラップや鉄くずの売却収入
・祝い金・祝儀など
・税金の還付金・還付加算金
売上に対して雑収入が多いと、会社の本業が分かりづらくなります。場合によっては、税務署から脱税を疑われるかもしれません。雑収入が多い場合は、個別に別途勘定科目を設けるなどして対処しましょう。
未収金を決算処理する際のポイント
未収金の発生頻度は売掛金と比べて少ないですが、固定資産や有価証券を売却した場合、金額が大きくなることも珍しくありません。売掛金と同等の注意を払い、適切な会計処理を行いましょう。ここからは未収金を決算処理する際に押さえておくべきポイントをご紹介します。
発生主義で会計処理をする
収益や費用の記録方法には「発生主義」「現金主義」「実現主義」があります。それぞれの仕組みは以下の通りです。
| 仕組み | メリット | デメリット | |
| 発生主義 | 費用や収益が発生したとき(売上額や支出額が確定したとき)に仕訳を行い記帳する方法 | 入出金がまだ行われていない取引も把握できるため、将来の資金繰りを考えやすい | 入出金の実態が分かりづらく、会計処理が複雑になる |
| 現金主義 | 現金や預金などのお金が動いた際に仕訳を行い記帳する方法 | 帳簿付けが単純で、不正を防ぎやすい | 財務状況を把握しづらい |
| 実現主義 | 収益や費用の実現が確定したとき(実際に商品が納品されたときなど)に仕訳を行い記帳する方法 | 利益や費用を把握しやすく、会計期間をまたいだ処理ができる | 会計処理が複雑になりやすい |
発生主義と現金主義は対立する概念で、実現主義は発生主義に修正を加えたものと考えられます。未収金の会計処理は通常、発生主義に基づいて行います。現金主義では売却損益や債権残高が確認しづらいなどのデメリットがあるためです。
取引先の財務状況や回収予定残高を確認する
未収金は売掛金同様に債権の一種であるため、適切に管理を行わないと貸し倒れが発生するかもしれません。売掛金を回収するためのリスク管理を与信管理といいますが、この考え方は未収金の回収にも役立ちます。取引先の財務状況や回収予定残高を事前に明確にしておけば未回収リスクを減らせる上に、万が一支払いが遅れた場合も適切な対応が取りやすくなります。
未収金の支払い遅れが発生した場合は、まずは自社側に不備がないか確かめましょう。正しく事務処理をしているつもりでも、実は請求書を送っていなかったり、宛先が間違っていたりすることもあります。
自社側に特に落ち度がない場合はメールや電話で催促を行いましょう。それでも効果がない場合は、段階に応じて督促状の送付や法的措置を行ってください。ただし、法的措置を行う際には手間も費用もかかるため、最終手段と考えた方がよいでしょう。
なお、未収金が回収できなかった場合は、貸倒損失として計上します。例えば、未収金が100万円あったものの、裁判所の決定により法律上消失してしまった場合は、以下の通り仕訳をしてください。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 貸倒損失 | 1,000,000円 | 未収金 | 1,000,000円 |
経過勘定処理をする
もし未収益金(未収収益)を未収金として管理している場合は、経過勘定処理を行います。経過勘定処理とは、既に商品やサービスを提供しているにもかかわらず、現金の移動がない場合に行う仕訳のことです。
例えば、会計年度が4月1日〜翌年3月31日の企業で、2025年1月1日から月額家賃10万円で不動産を貸し出して代金の回収は1年後にまとめて行うとします。この場合、決算日(2025年3月31日)時点で不動産を貸し出してから3カ月経過しており、賃料も発生しているにもかかわらず、代金は受け取っていません。このようなケースでは、まず期末である2025年3月31日に以下のように仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 借方 | 金額 |
| 未収収益 | 300,000円 | 受取家賃 | 300,000円 |
これにより、2024年度に3カ月分の受取家賃が計上されました。
次に、期首である2025年4月1日に以下のような仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 受取家賃 | 300,000円 | 未収収益 | 300,000円 |
最後に、2025年12月31日に実際に家賃を受け取ったら、以下のような仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 1,200,000円 | 受取家賃 | 1,200,000円 |
この一連の仕訳により、2024年度には30万円(3カ月分)、2025年度には90万円(9カ月分)の受取家賃がそれぞれ計上されました。経過勘定処理を行うことにより、実態に即した受取家賃の配分が行われたわけです。
買掛金と相殺される場合があることを認識する
買掛金とは、企業の営業活動に伴って発生する債務のことです。例えば、掛取引で仕入を行った場合には買掛金が発生し、債務を履行する(現金を支払う)義務を負います。未収金は債権、買掛金は債務という対の関係があり、条件を満たした場合には双方を相殺可能です。適切に相殺すれば、資金繰りの改善や決済リスクの軽減につながります。
一方で、不適切な相殺は法的なリスクになります。知識が曖昧な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
相殺の条件
未収金と買掛金は、法律上認められており、なおかつ当事者が合意している場合に相殺できます。例えば、自社が取引先に対して50万円の未収金を持っている一方で、買掛金(取引先から見れば売掛金)が30万円あるとします。この場合、両者が合意すれば、自社が取引先から20万円を回収するだけで、金銭のやりとりを終わらせられるのです。
ただし、契約時に相殺禁止の特約を定めている場合は、その後事情が変わっても相殺できません。また第三者の権利を侵害する相殺は無効となる他、回収時期が異なる債権同士を相殺する場合は注意が必要です。
相殺をしたい場合は書面で通知します。通知が取引先に伝わった時点で効力が生じ、その後相殺する金額を減額すれば手続きは完了です。
スピーディに未収金の回収を行うべき理由
未収金の回収はできる限り早く行いましょう。回収遅れは財務状況の悪化、ひいては倒産につながるリスクがあります。
黒字倒産に陥るリスクがある
黒字倒産とは、損益計算書上は黒字にもかかわらず、手元資金が用意できずに倒産してしまうことです。黒字倒産の主な原因は、利益の発生と現金の出入りのタイミングの差異です。
企業間取引は通常、掛取引で行われます。売上が発生してから実際の入金に数カ月かかることも珍しくありません。この数カ月の間に会社を運営するための資金がなくなれば、会計上黒字であっても倒産してしまいます。未収金がある場合は確実に、なるべく早く回収しましょう。
黒字倒産を防ぐ上で重要なのが、適切なキャッシュフロー管理です。キャッシュフローとは簡単にいえば現金(預金などすぐに現金化できるものを含む)の流れのことです。毎月どこからどれだけのお金が流れてきて、どこにどれだけ流れていくのかを把握しておけば、黒字倒産のリスクを減らせます。その他、回収サイクルの短縮や与信管理も、黒字倒産の防止につながるでしょう。
時効になるリスクがある
未収金は、以下のいずれかの条件を満たした場合には時効となり消滅します(※)。
・債権者が権利を行使できると知った日から5年間行使しなかった場合
・債権者が権利を得てから10年間行使しなかった場合
「権利を行使できる」と知らずに権利を得るケースは少ないので、通常は5年で時効が来ると考えてください。なお、裁判上の請求を行っていたり、一部支払いをしていたりするした場合には時効がストップもしくはリセットされます。
未収金を回収する方法
未収金を含む債権の未払いが続いても、すぐに法的手段に出るのは控えた方がよいでしょう。時間もお金もかかる他、相手が自分の意思で支払ってくれるならそれに越したことはありません。まずは、メールや電話での催促といった手段で支払いを要請しましょう。それらの手段ではうまくいかない場合は、徐々に別の手段に切り替えていきます。詳細についてご紹介します。
督促状を送る
メールや電話での催促がうまくいかなかった場合は、督促状を送りましょう。催促と督促はどちらも法的な効果のない、支払いを促す行為ですが、督促の方がより強い意味合いを持ちます。催促は「依頼」、督促は「応じない場合に法的措置を取るという事前通知」と考えると分かりやすいかもしれません。
督促状の書き方に決まった形式はありませんが、法的手段を取る際の証拠にもなるため、事実を簡潔に記載しましょう。誰が、いつ、誰に対して、何のために発行したかは特に大切な事柄なので、忘れずに記載してください。
作成した督促状は、内容証明郵便で送信しましょう。内容証明郵便は郵便局が提供するサービスの一つで、誰が、いつ、誰に対して、どのような内容の郵便を送ったかを証明できるものです。また配達証明(確実に相手に届けたことを証明する仕組み)を併せて使えば、債務者は「督促状は受け取っていない」という言い訳ができなくなります。
債務者と交渉する
督促状を送っても効果がなかった場合は、債務者との直接交渉も検討しましょう。直接会うことにより相手方の経営状態を大まかに把握できる他、与えるプレッシャーも大きくなります。また債務の存在を相手に認めさせれば、時効をリセットできます。債務を認めさせる際には、書面で記録を残すようにしましょう。
ただし、直接交渉する際には注意点もあります。例えば未収金の金額が少なく、なおかつ相手が遠方にいる場合は、時間とお金を掛けてまで直接交渉する価値があるのかを判断しなければなりません。明らかに相手に支払いの意思がなさそうな場合も、交渉をせずに法的手段に移った方がよいケースもあります。
何度も訪問したり、深夜や早朝に訪問したりするのは不法行為に該当する恐れがあります。その場合、逆に相手から訴えられかねません。事前に約束を取り付けるなどの配慮を忘れないようにしましょう。
法的措置を取る
相手が支払う態度を全く見せない場合は、法的手段も視野に入れましょう。未収金回収の際に利用できる主な法的手段は、以下の通りです。
| 法的措置の種類 | 概要 |
| 支払督促 | 支払督促は、簡易裁判所の書記官から相手方に督促してもらう仕組み書類審査のみで手続きでき、裁判所の名前が出るため、債権者自ら行う督促よりもプレッシャーを与えやすい2週間以内に相手方が異議申し立てをしてこなければ仮執行宣言の申し立てが行われ、さらに2週間以内に異議が出なければ裁判の判決と同等の効力を持つ異議申し立てがあった場合は訴訟に移行する異議申し立てのリスクが高い場合には最初から訴訟をした方が無駄なコストを減らしやすい |
| 公正証書 | 公正証書は、公証役場で作成・保管される書類のこと強制執行認諾文言付公正証書を事前に作成しておけば、債務者が債務を履行しなかった際に裁判なしで強制執行できるただし、事前に双方で同意して公証役場で作成しておかなければならない |
| 民事調停 | 民事調停は、裁判官や民間人の調停委員を交えて話し合いを行う仕組み話し合いが成立すれば調停調書が作成される。調停調書は、判決と同等の効力を持つ調停が不成立に終わると強制執行ができない |
| 訴訟(少額訴訟) | 確定判決が出れば、それに基づいた強制執行ができる請求額が少ない場合は、判決が迅速に出る少額訴訟も使える |
上記の方法により強制執行ができるようになったら、強制執行申し立てを行い相手の資産を差し押さえて回収します。
まとめ
未収金は、企業の主たる営業活動以外の反復性のない活動で発生する債権です。後に回収する代金という点では売掛金と似ていますが、売掛金は本業で得た債権、未収金は本業以外で得た債権という違いがあります。
未収金は固定資産や有価証券を売却した場合にも発生するため、金額が大きくなることも多いです。契約前に取引先の財務状況や回収予定残高を確認しましょう。
未収金の未払いが続く場合、催促などをしてもうまくいかない場合は、督促状や交渉、そして法的手段を視野に入れてください。
未収金が回収できず、資金繰りが一時的に悪化した場合は、ファクタリングサービスを使うのも選択肢の一つです。ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に売却する信金調達方法で、融資と比べて審査のハードルが低く、最短即日で入金が受けられるというメリットがあります。
株式会社 Mentor Capitalは年間3,000件以上の取引実績と、審査通過率92%の柔軟な対応が特長のファクタリング会社です。赤字や債務超過、税金滞納などの場合や他社で断られた場合でも、対応してもらえる可能性があります。資金繰りにお困りの方は、お気軽にご相談ください。