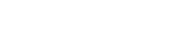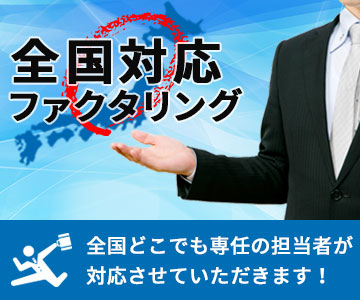給料日が遅れるのは違法! 罰則などリスクと回避する方法を解説
最終更新日:2025年03月31日
労働基準法では、従業員に支払う賃金(給料)に関するさまざまなルールが定められています。中でも給料の支払い遅れには厳しいルールがあり、理由に関係なく一日でも遅れた時点で労働基準法違反です。また罰金などの罰則がある他、遅延損害金も発生するなど、さまざまな不利益を被ることになります。場合によっては企業の経営が大きく傾くため、給与未払いは防がなければなりません。
今回の記事では、給料日に遅れることがなぜ違法行為と見なされるのか、どのような罰則や不利益があるのか、支払いが遅れそうな場合にはどうすれば良いのかなどを解説しています。
Table of Contents
給料日が遅れるのは違法?
従業員への給料の支払いが遅れるのは労働基準法第24条違反です。詳細は後述しますが、従業員に対する給料の支給方法にはいくつかの守るべき「ルール」があります。給料日に給料を支払わなかった場合、このルールに抵触し、違法行為になるため、注意が必要です。仮に従業員が年俸制で働いている場合でも、給料日に支払いを行わなければなりません。
給与未払いが発生した場合、労働基準法や最低賃金法に基づいた罰金が発生する他、悪質な場合は告訴・逮捕、懲役刑などに至る可能性があります。また給与未払いに対しては遅延損害金が発生するため、結果的により多くの経費を払うことになります。給与未払いは極力避けなければなりません。
罰則対象になる賃金の種類
罰則の対象となる賃金(給料)は、毎月の給与だけではありません。以下の報酬に関しても前述のルールが適用されるため、給与未払いが発生した時点で違法となります。
・あらかじめ支給基準や金額の決定方法が明確にされている一時金(ボーナスなど)や退職金
・休業手当
・割増賃金(時間外労働や休日労働に対して上乗せされる賃金)
・年次有給休暇の賃金
・その他、労働基準法第11条において定められているもの
事業者が従業員に対して「労働の対償」として支払うものは、全て労働基準法の賃金に含まれ、給与未払いを起こした場合は罰則の対象となります。逆に、労働の対償には当たらないものは労働基準法の賃金に当たりません。例えば事業者に支払い義務がなく、任意で給付する死亡弔慰金や災害見舞金、あるいは社宅の貸与や給食などは賃金には含まれません。
給料の遅配に関する時効制度
給与未払いに対する従業員の賃金債権には時効があり、時効が成立した場合、従業員は賃金を請求できなくなります。時効の期間は労働が行われた時期によって異なります。
・2020年4月1日以前が支払期限の給料:2年
・2020年4月2日以降が支払期限の給料:5年(当分の間経過措置として3年)
・退職金は時期に関わらず5年
なお、時効があるからといって給料の支払いから逃れようとするのは推奨できません。給与未払いには社会的信用の毀損や離職率の増加など、多くのリスクが存在するためです。
給料の支払いに関するルール
労働基準法では、給料の支払いについて4つのルールが定められています。従業員に対して給料を支払う場合は、以下の4つのルールを遵守しましょう。
月1回以上決められた日に支払う
給料は少なくとも毎月1回以上、日を特定して支払わなければなりません。そのため、例えば「今月は資金繰りが厳しいので、来月に2カ月分の給料をまとめて支払う」といったようなことはできません。
なお、給料日の設定は会社側が行えます。毎月「1日」でも「13日」でも「27日」でも問題ありませんが、多くの会社は「10日」「15日」「25日」など、下1桁が0もしくは5の日に定めているようです。
また給料日の振込時間は労働基準法で定められていませんが、労働基準監督署は「午前10時までに引き出せるようにしなければならない」と指導を行っています。そのため、多くの企業は銀行の始業時間である午前9時には引き出せるようにしています。
通貨で支払う
給料は通貨で支払わなければなりません。通貨とは「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で定められている、いわゆる「日本円」です。日本円に該当しないもの、例えばドルやユーロ、あるいは仮想通貨など、日本円に該当しないものでの支払いは禁止されています。法令や労働協約に定めがある場合のみ、現物支給が可能です。
また給料の支払いは原則現金で支払わなければならないと定められています。ただし、従業員が同意しているなど所定の条件を満たしている場合は、金融機関への振込で支払うことも可能です。給料の直接手渡しには紛失や盗難のリスクがあるため、多くの企業は振込を利用しています。
全額を支払う
給料は原則として全額を本人に支払わなければなりません。要するに、会社都合で勝手に「積立金」などの名目で天引きをしてはいけないのです(法令で定められている所得税や社会保険料の控除は可能)。
会社都合で何らかの天引きを行う場合は、労働者の過半数によって組織されている労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と労使協定を結ぶ必要があります。
本人に直接支払う
給料は労働者本人に直接支払わなければいけません。例えば労働者の親権者や法定代理人、委任を受けた任意代理人などへの給料の支払いは労働基準法違反であり、支払いは無効となります。
ただし、使者への支払いは可能です。代理人は不可で使者は可、というのは少し分かりにくいかもしれません。実際、両者を完璧に区別するのは困難ですが、通常は本人に支払うのと同一の効果が望めるか否かで判断を行います。例えば従業員本人が病気などで受け取れない場合、配偶者を使者にできるでしょう。
また裁判所から労働者の賃金差し押さえの指示が出ている場合は、直接債権者に支払うことになります。
給料日が遅れることによる企業が抱えるリスク
前述の通り給与未払いは違法行為であり、さまざまな罰則の対象になりますが、リスクはそれだけではありません。給料日の支払いが遅れることによる主なリスクは以下の4つです。
社会的信頼が損なわれる
給料の支払いが遅れると、企業の社会的信頼は当然失われます。事情はどうであれ労働の対価である給料を支払わないという違法行為を行う企業が、取引先や顧客、株主や従業員から信頼されるはずもありません。
給与未払いの情報が外部に流出しない確証もありません。このSNS時代において、従業員がX(旧Twitter)や企業の口コミサイトで自らの勤務先の給与未払いを明かすことも考えられます。そうなった場合、新たな人材採用にも悪影響が出て、企業の収益性が低下し、給与未払いが再び発生するという負のスパイラルに陥ることも十分あり得るでしょう。
罰金や遅延損害金が科せられる
給与未払いが発生した場合、労働基準法および最低賃金法に基づいて罰金が科されるケースがあります。罰金は労働基準法が30万円以下、最低賃金法が50万円以下です。割増賃金の未払いがあった場合は、それとは別に6カ月以下の懲役刑が科されます。
また給与未払いがあった場合、金額と期間に応じて遅延損害金を支払わなければなりません。遅延損害金は年利3%で、例えば1カ月遅れた場合は3%÷12=0.25%となります。
一見すると大したことない利率に見えるかもしれませんが、従業員が多ければ遅延損害金の金額も膨らみます。例えば月給25万円の労働者に対する遅延損害金は25万円×0.25%=625円ですが、従業員が10人なら6,250円、100人なら62,500円です。決して少ない金額ではなく、資金的にも大きな痛手といえるでしょう。
従業員のモチベーション低下・離職につながる
給料の支払い遅れは、ほぼ確実に従業員のモチベーション低下につながります。従業員は当然、給料日に給料が支払われることを前提に毎月の支払いの計画を立てています。その前提を裏切れば、たとえ一度の遅延でも、当然不信感は高まるでしょう。
モチベーションの低下は、従業員のサボタージュや仕事の手抜きにつながります。そうなれば事業の収益性が低下し、手元の資金が減少し、給料の支払いが再び遅れるという悪循環に陥ってしまいます。最終的に従業員は会社を見限り、離職していくかもしれません。ノウハウを持った従業員が離職すれば、新たな人材の採用・育成コストがかかります。
訴訟を起こされる
給与未払いが発生した場合、弁護士を雇った従業員から訴訟される恐れがあります。給与未払いについては通常の民事訴訟で争われることもありますが、時間がかかるため一般的には以下の手続きが使われることが多いです。
・少額訴訟:60万円以下の請求で利用できる。原則1回の審理で終わる
・民事調停:非公開の話し合いによって解決を目指す。裁判所の調停委員会が斡旋する
・支払督促:書類審査で行う手続き。会社が異議を申し立てた場合は民事訴訟になる
・労働審判:労働関係の紛争を争う手続き
訴訟は正社員のみならず、契約社員やアルバイトなど雇用形態に関係なく起こせるものです。給与未払いになっている全従業員から一斉に訴訟を起こされる可能性も否定できません。
労働基準監督署に介入される
従業員が給与未払いを労働基準監督署に訴えた場合、調査や介入によって労力を費やすことになります。ただし、従業員が訴えた時点ですぐに介入が起こるわけではありません。
従業員から告訴状を受け取った労働基準監督署は、会社に対して給料の支払いを促します。この時点で会社が支払いを行えば、介入はありません。ただし、給与未払いが続いた場合、労働基準監督署は立ち入り調査や行政指導を行います。
調査では事情聴取や帳簿などの資料の提出が求められます。こうした手続きに時間が取られれば本業にかけられる時間が少なくなり、さらに業績が悪化するでしょう。
給料日が遅れないようにする9つの方法
ここまで紹介してきた通り、給料日に支払いが遅れるのは明確な違法行為であり、さまざまな罰則があります。また従業員や取引先からの信頼も失うため、極力避けなければなりません。確実に給料日に給料を支払うためにも、以下の方法を実施しましょう。
1. 管理システムを導入する
給料の遅れは、理由に関わらず違法となります。うっかり給与未払いを起こさないためにも、適切な勤怠管理システムを導入しましょう。勤怠管理システムとは、各従業員の出退勤時刻の記録、残業や休暇申請、シフト作成、残業時間や休日出勤の有無の管理などを一元的に行うためのシステムです。
かつてはタイムカードやExcelで勤怠管理をする企業が多かったですが、近年は手間がかからずミスも生まれづらい、勤怠管理専用のシステムを導入する企業が増えてきています。
勤怠管理システムには、自社のサーバーにシステムを構築する「オンプレミス型」と、インターネットに接続して使う「クラウド型」があります。オンプレミス型はセキュリティ性に優れ、クラウド型は安価で使えるというメリットがあり、どちらも一長一短です。
最新の勤怠管理システムは生体認証やQRコードを用いた打刻、残業超過に対するアラート機能、不正防止のためのGPS機能など独自の性能を持つものも多いです。自社の規模やニーズに合わせて、適したものを選びましょう。
2. 支払いの優先順位を見直す
企業は事業を行うに当たって、買掛先や金融機関、従業員や国・自治体などさまざまな関係者に対してお金を支払っています。もちろん全ての関係者に対して滞りなく支払えるならばそれに越したことはありませんが、経営が行き詰まってくるとそうもいきません。
用意できる資金が限られている場合は、まずは支払いの優先度が高い(支払いが遅れたときの不利益が大きい)ところに対して支払いを行い、そうでないところは後回しにした方が良いでしょう。会社が行う支払いは大きく7種類に分類できますが、通常は以下のように優先順位を付けます。
・手形の支払い
・従業員への給料
・買掛金
・給料以外の諸経費(水道光熱費など)
・金融機関への支払い(利息部分)
・税金・社会保険料
・金融機関への支払い(元本部分)
企業が最優先すべきは、ずばり手形の支払いです。手形は、取引先に対して決められた期日に支払いを行うと約束する際に発行する有価証券です。取引先は銀行に手形を持ち込めば、現金を受け取れます。手形の支払いが滞ることを不渡りといい、1回目の不渡りから半年以内に2回目の不渡りを起こすと金融機関と取引ができなくなります。金融機関との取引の停止は事実上の倒産になるため、最優先して支払いましょう。
次に優先度が高いのが従業員の給料です。前述の通り、給料の遅れは違法であり、さまざまな罰則があります。給料が遅れたことが知られれば社会的信頼も失われるため、手形の次に優先して支払いましょう。
買掛金は仕入先に事情を話せば、少し待ってもらえるかもしれません。ただし、その場合でも全額をいきなりストップするのではなく、半分だけ支払うなどの工夫が必要になります。また、何度も支払いを待ってもらおうとすると取引そのものを打ち切られるかもしれません。
水道光熱費などは、1~3カ月程度なら支払いが遅れてもすぐに止められることはありません。もちろん、事前の連絡は必要です。
銀行に対する支払いは、元金部分は1~2年程度なら据え置いてもらえることが多いです。ただし、利息の支払いまで止めてしまうと格付けが大幅に下がるため、利息だけは支払い続けた方がいいでしょう。
税金や社会保険料は、滞納総額が1000万円程度までならばある程度待ってもらえることが多いため、税務署や市区町村役場に相談しましょう。督促を無視し続けると強制執行に至るため注意が必要です。
3. 給与を管理する担当者への教育を徹底する
前述の通り適切な勤怠管理システムの導入は大切ですが、いくら優れたシステムを導入しても、使いこなせなければ適切な管理ができません。新しいシステムを導入する際には、スタッフに対して適切な指導、トレーニングを行いましょう。必要に応じて、研修や勉強会を開くことも大切です。
専門の担当者を採用する余裕がない場合は、外注しても良いでしょう。勤怠管理のノウハウのある会社に業務を任せれば、本業に集中しやすくなるというメリットもあります。
4. 勤怠管理などの社内体制を整える
前述の通り勤怠管理システムの導入は有用ですが、それをスムーズに運用するための社内体制の構築も忘れてはいけません。どの部署が、どのような方法で、何を目的に運用するかを明確にしておきましょう。
勤怠管理を行う部署は企業によって異なりますが、一般的な企業の場合は総務、労務部門が行うことが多いです。
導入する勤怠管理システムは一概に何がベストとはいえませんが、管理者と従業員の双方が使いやすいものを選ぶとトラブルや不正を防ぎやすくなります。また他の基幹システムとの連携も重要です。給与計算ソフトと連携できるものを選べば、計算ミスを効率的に防げるでしょう。
5. 定期的に内部監査を実施する
定期的な内部監査の実施は、給料日の支払い遅れを防ぐのに役立ちます。内部監査とは、企業内に存在する独立した組織が、財務会計や業務の調査・評価・報告を行うことです。一定以上の資本金や負債を持つ大企業、新規上場企業などは内部監査の実施が義務付けられています。中小企業も、任意で内部監査を実施可能です。
内部監査を定期的に行うと、給料の支払処理のプロセスや、導入している勤怠管理リシステムの欠点を特定できます。内部監査は給料の支払い遅れを防ぐのにはもちろん、不正の防止や業務の効率向上などにも寄与するため、実施が義務付けられていない企業であっても積極的に実施した方が良いでしょう。
6. 役員報酬を減額する
役員報酬を減額して、従業員に支払う給料を確保するという手段もあります。通常、役員報酬は事業年度開始から3カ月以内の改定が求められますが、業績が著しく悪化したなどの理由がある場合は、期の途中でも減額が可能です。その場合は、役員会議での決議を行いましょう。
7. 借入金支払いのリスケジュールをする
資金繰りが厳しく、給料の支払いが遅れる可能性が高い場合は、借入先の金融機関にリスケジュールの交渉を持ちかけてみましょう。リスケジュールとは、支払いが厳しくなった場合に、金融機関に対して毎月の支払額や支払期間の変更を求めることです。リスケジュールの交渉の際に提出する経営改善計画が金融庁のマニュアルや監督指針に基づいて作成されている場合、金融機関は原則としてリスケジュールを断れません。
金融機関にとっても、リスケジュールを断って倒産されて不良債権を抱えるよりは、リスケジュールに応じて経営を立て直してもらった方が良いため、誠意を持って応じれば対応してもらえる可能性が高いでしょう。
ただし、リスケジュールの期間は最長でも1年程度です。この期間中に資金繰りの悪化を改善できなかった場合、銀行は債権を債権回収会社に売却する可能性が高いです。またリスケジュールの実施は、信用格付けの低下につながる恐れもあります。
8. 専門家のコンサルティングを受ける
自社だけで給与未払いを防ぐのが難しい場合は、外部の専門家を採用したり、コンサルティングを受けたりすると良いかもしれません。特に給与体系が複雑で、内部の社員でも完璧に把握しきれていない場合は、会計事務所などの力を借りると問題を解決しやすくなります。ただし、一口に会計事務所といっても得意分野が異なる点には注意が必要です。
9. 資金調達をする
上記の方法を試してもなお資金繰りが厳しく、給料を支払えそうにない場合には、資金調達を行いましょう。企業が利用できる資金調達は多数ありますが、いざというときに活用しやすいのは以下の4つです。
日本政策金融公庫による融資
日本政策金融公庫は、中小企業や小規模事業者を対象とした財務省管轄の政府系金融機関です。日本政策金融公庫は以下の3種類の融資を行っています。
・一般貸付:ほとんどの業種が利用できる
・特別貸付:特定の要件に当てはまる場合に利用できる
・生活衛生貸付:理容室やクリーニングなどの生活衛生関係で利用できる
日本政策金融公庫による融資のメリットは、無担保・無保証人でも比較的利用しやすいことです。例えば一般貸付の場合、無担保融資の融資限度額は4800万円となっています。民間の銀行や信用金庫では保証人を求められることが多く、日本政策金融公庫ならではのメリットです。弁済期間も長めに設定されているため、余裕のある弁済計画を立てやすいです。
一方で、審査期間が長いため、緊急時の利用には適さない一面もあります。
銀行・信用金庫による融資
民間の銀行や信用金庫からの融資は、企業の資金調達手段でも特にポピュラーなものです。これらの融資は、直接借り入れる「プロパー融資」と、信用保証協会に対して保証料を支払い、弁済できなくなった場合に立て替えてもらう「保証付き融資」があります。プロパー融資は審査が厳しいため、実績に乏しい中小企業の場合は保証付き融資を利用することになるでしょう。
銀行や信用金庫からの融資のメリットとして、金利が低いことが挙げられます。企業の信用力にもよりますが、後述するビジネスローンよりは低金利で借りられることが多いです。また、滞りなく支払いを行えば信用力が増すため、次回以降の借り入れで有利になります。
一方で、担保や保証人を求められることが多いというデメリットもあります。
ビジネスローン
ビジネスローンは、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などが提供している事業者向けのローンです。金融機関からお金を借りるのは銀行融資と同じですが、こちらは利用枠の範囲内で繰り返し借り入れられるという特徴があります。
ビジネスローンのメリットとして、申し込みから融資実行までの期間が短いことが挙げられます。最近は最短即日融資が可能なビジネスローンも増えてきているため、緊急で資金が必要になったときに便利です。また担保や保証人が不要なケースが多いため、十分な資産を持たない中小企業でも利用しやすいです。
一方で、金利は日本政策金融公庫や銀行の融資などと比べるとかなり高めに設定されています。また借入限度額も低く設定されているため、あくまでも一時的な資金繰り悪化を凌ぐためのものと考えた方がいいでしょう。
ファクタリング
ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却して早期に現金化する仕組みです。通常、売掛債権を現金化するには支払期日まで待つ必要がありますが、ファクタリングを利用すれば支払期日よりも前に現金を用意できます。ただし、利用には手数料がかかるため注意が必要です。
ファクタリングは、売掛先の同意なしでも行える「2社間ファクタリング」と、売掛先の同意が必要な「3社間ファクタリング」に分けられます。2社間ファクタリングはファクタリング会社の負うリスクが高くなる分手数料が高くなりますが、手続きにかかる時間が短く、売掛先にファクタリングの利用を知られないというメリットがあります。3社間ファクタリングは多少時間がかかる反面、手数料が安いのがメリットです。
ファクタリングのメリットとして、資金を素早く確保できることが挙げられます。2社間ファクタリングの場合、即日入金にも対応してもらえることが多いです。また売掛金を売却する仕組みであり、融資ではないため、担保や保証人も必要なく、場合によっては赤字でも利用できます。
手数料は銀行融資の利息などと比べると高めですが、資金を素早く確保したい場合には有力な選択肢となるでしょう。
まとめ
給料日の支払いが遅れるのは理由に関係なく違法行為であり罰金の対象になります。また遅れた期間と金額に応じて遅延損害金が発生します。毎月の給料はもちろん、割増賃金や休業手当などの遅れも罰則の対象になるため注意が必要です。
給料日の支払いが遅れないようにする方法はいくつかあります。適切な勤怠管理システムの導入と運用、内部監査の実施、役員報酬の減額なども有力な手段ですが、手元資金に余裕がないことが遅れの原因の場合は、資金調達を行って給与支払いへの原資に充てると良いでしょう。
資金調達手段の中でも、特におすすめなのがファクタリングです。ファクタリングは日本政策金融公庫や銀行などの融資と違い、返す必要がありません。ファクタリング会社は複数ありますが、中でもMentor Capitalには最大買取率98%、審査通過率92%、最短即日入金可能という強みがありおすすめです。他社で断られた方でも相談可能なため、まずはご連絡ください。