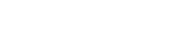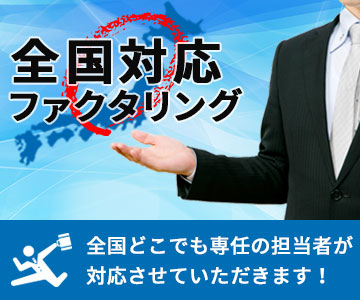不渡りとは? 意味や仕組み、回避する方法を簡単に解説
最終更新日:2025年10月29日
不渡りとは、振り出した手形や小切手が決済できなくなることです。当座預金不足などが原因の不渡りを短期間に複数回出すと銀行での取引ができなくなり、実質的な倒産状態に追い込まれてしまう恐れもあります。
本記事では、ファクタリングの意味や種類、不渡りを起こしてしまった場合の影響、回避する方法などについて分かりやすく解説します。
<この記事で分かること>
・不渡りの意味
・不渡りが振出人や受取人に与える影響
・不渡りを回避する方法
・万が一不渡りを起こした場合の適切な破産手続きの方法
Table of Contents
不渡りとは? 意味や仕組みを解説
不渡りとは、企業が振り出した手形や小切手が決済できなくなる状態のことです。
手形や小切手は、企業が支払いのために発行する有価証券です。振出人(代金を支払う側)が発行し、必要な情報を記入して受取人(代金を受け取る側)に渡します。現金化できるタイミングで受取人が銀行に手形や小切手を持ち込むと、振出人の当座預金口座から所定の金額が引き落とされ、受取人に渡されます。
ただし、手形や小切手の記載に不備があったり、当座預金の口座が不足していたりした場合は決済ができません。これを不渡りといいます。不渡りの原因によっては振出人の信用力が大きく毀損し、銀行取引が停止されることもあるため注意が必要です。
ちなみに、当座預金は企業や個人事業主が事業のために保有する口座です。審査があるため誰でも無条件で開設できるわけではありませんが、それゆえに開設できただけでも、信用力を認められたといえます。
不渡りの種類
不渡りは大きく以下の3種類に分類できます。
・0号不渡り
・1号不渡り
・2号不渡り
単に「不渡り」という場合は、1号不渡りを指すのが通常です。本記事でも基本的に「不渡り=1号不渡り」としてご紹介しています。
ここからは3種類の不渡りについて、詳しく見ていきましょう。
0号不渡り
0号不渡りは、振出人の信用力とは直接関係のない事由などによって発生する不渡りです。具体的には、以下のようなケースが該当します。
・受取人が決済日よりも前に換金しようとした
・受取人が受け取り可能な期間を過ぎてから換金しようとした
・手形に記載漏れなどの形式上の不備があった
0号不渡りも避けるに越したことはありませんが、振出人の信用力に問題があると判断されるわけではありません。そのため、不渡届提出や取引停止処分の対象にはなりません。
1号不渡り
1号不渡りは、振出人の信用力不足によって発生する不渡りです。具体的には、以下のようなケースが該当します。
・振出人の当座預金残高が不足している
・振出人が銀行の口座を保有していない(解約した)
先述した通り、通常、不渡りとはこの1号不渡りのことを指します。
2号不渡り
2号不渡りは、0号不渡り・1号不渡りのどちらにも該当しない不渡りです。具体的には、以下のようなケースが該当します。
・振出人がだまされて手形が発行された
・手形や小切手が偽造・変造された・盗まれた
・契約不履行があった(手形を振り出したのに商品が納品されなかったなど)
2号不渡りでは1号不渡りと同じく、不渡届が作成されます。ただし振出人の信用力が原因ではない不渡りであるため、異議申し立て(猶予の獲得)が可能です。異議申し立てをする場合は、手形や小切手の金額を預託金として提供します。
偽造や変造などが理由の場合は、事実を証明する書類を提出できれば預託金が免除されます。異議申し立てを行わないと1号不渡り同様に処分が下るため注意してください。
不渡りによる影響
不渡りは振出人・受取人双方に多大な悪影響を与えます。特に振出人側の企業は不渡りが原因で事実上の倒産に至ることもあります。ここからは振出人が受ける影響と、受取人が受ける影響を見ていきましょう。
振出人が受ける影響
当座預金残高不足などが原因で不渡りが出た場合、振出人の信用力が失われます。1回目の不渡りが発生した場合、銀行は電子交換所に不渡届を提出します。電子交換所は紙の手形を搬送していた手形交換所を電子化したものです。電子交換所は加盟金融機関に対して、不渡りが発生した通知を行います。つまり、不渡りを起こしたことが金融機関に知られるわけです。
金融機関としては不渡りを起こすような会社には融資を行いたくないため、借り入れは極めて難しいものになります。不渡りを起こしたからといって即倒産するわけではありませんが、資金繰りが厳しくなることを認識しておきましょう。
1回目の不渡りから6カ月以内に2回目の不渡りを出した場合は、銀行取引停止処分が下されます。この場合、2年間金融機関との当座預金取引ができなくなる他、融資も受けられません。手形や小切手を介した取引を行う企業にとっては致命的な事態であり、2回目の不渡りは事実上の倒産と見なされることも多いです。
また銀行取引停止処分は、上場廃止事由に該当します。そのため上場企業が不渡りを起こした場合は、上場廃止が決定された銘柄である「整理銘柄」の指定を経て上場が廃止されてしまうのです。
受取人が受ける影響
受取人は保有していた手形や小切手を換金できなくなるため、金銭的な損害を被ります。もちろん、不渡りが出ても債権が消滅するわけではないため、債務の履行を求めて訴訟を起こすことは可能です。また手形が裏書きされた(譲渡された)場合は、裏書人(振出人ではなく手形の裏書きをした人)に対して支払いを求められます。
ただし、いくら訴訟をしたところで、相手に支払能力がなければ十分な回収は見込めないでしょう。そもそも振出人に十分な支払能力がある場合は、不渡りを起こさないはずです。回収の見込みが薄い債権のために、余計な時間や費用を払うのは考えものです。
手形や小切手を介した取引をする場合は、十分な与信管理を行いましょう。また万が一、不渡りが発生したときに備えて、十分な資金を用意しておくことも大切です。取引先が起こした不渡りが原因で、受取人である企業まで連鎖倒産しないように対策を講じておきましょう。
不渡りになると企業は倒産する?
不渡りを起こした企業が100%倒産するわけではありません。ただし、不渡りを出した企業が倒産しやすくなるのも事実です。
先述した通り、1回目の不渡りの時点では不渡りを起こした事実が金融機関に広く知られます。そのため、融資は受けにくくなりますが、完全に不可能というわけではありません。またそもそも融資が必要ない状況ならば、乗り切れる可能性は十分あるでしょう。
しかし、6カ月以内に2回目の不渡りを出して銀行取引停止処分が下されると、事業の存続は難しくなります。もし全ての取引を現金で行えるなら問題ありませんが、実際にはそうはいきません。融資を受けている場合は、残債の一括弁済を求められることも考えられます。このような環境で銀行取引停止処分が解除される2年間を乗り切るのは難しいといえるでしょう。
不渡りを回避する方法
不渡りを起こしてしまうと、会社の信用力は大きく損なわれ、場合によっては倒産につながることもあります。不渡りが発生しそうな場合は、ここからご紹介する方法を試してみましょう。
ファクタリング
ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に売却して支払期日前に資金を得る、資金調達方法です。通常、売掛債権は支払期日にならないと現金化できませんが、ファクタリングを利用すれば早期に現金を受け取れます。ただし、利用の際には額面金額に応じた手数料を支払わなければなりません。
ファクタリングのメリットは、スピーディーに資金調達できることです。融資と比べると審査が易しめで必要書類も少なく、場合によっては即日で現金化できます。また融資ではないため、帳簿上の負債が増えることもありません。取引形態によっては、銀行や取引先に知らせずに利用可能です。
ファクタリングは、帳簿上は黒字であるものの一時的に資金繰りが厳しくなった場合に有用な資金調達方法です。借り入れせずに資金難を乗り越えたい場合は、利用を検討しましょう。ただし、頻繁に利用すると手数料がかさんでしまい、かえって経営が悪化する恐れもあります。利用するタイミングや状況をしっかりと見極めることが大切です。
過振り
過振り(かぶり)とは、銀行が手形や小切手の決済代金を一時的に立て替えてくれることです。銀行に依頼すれば、当座預金残高以上の支払いをしてもらえます。
ただし、過振りはあくまでも臨時的な措置であり、不足している金額が少額で、なおかつ取引実績が十分あり信用度が高い企業にしか適用されません。また過振りの依頼自体が信用度の低下につながる可能性も否定できません。もちろんそれでも不渡りを出すよりは望ましい選択ですが、あくまでも限られた優良企業だけが使える最後の手段であると認識しておいた方がよいでしょう。
手形のジャンプ
手形のジャンプとは、手形の受取人と交渉して、支払期日を当初よりも延ばしてもらう措置のことです。当事者同士の話し合いであるため、銀行に知られることはありません。交渉が成立した場合は既存の手形を修正するか、新しいものを振り出し直します。
ただし、資金繰りが危ういことが取引先に伝わるため、相応のリスクはあります。そもそも取引先にメリットのない提案であるため、無意味に終わる可能性も十分ある上、仮に交渉が成立しても受取人からの評価は下がるでしょう。交渉の際には会社の経営状況や資金繰りなどを丁寧に説明し、理解を得るようにしましょう。
不渡りを起こしてしまったときの対策
不渡りを出して企業を経営し続けるのが難しくなった場合は通常、法人破産の手続きを行います。法人破産は、債務を弁済できなくなったり、債務超過に陥ったりした場合に、保有している財産を処分(換価)して債権者に分配し、法人格を消滅させるための手続きです。
財産を処分してもなお、債務が残った場合は通常支払いを免除されますが、経営者保証(経営者が個人として企業の連帯保証人になること)をしていた場合はその限りではありません。
破産には同時廃止・少額管財事件・通常管財事件があります。法人の場合、同時廃止が選ばれることはほとんどありません。少額管財事件・破産管財事件で破産手続きを開始すると、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の財産や債権・債務を管理し、債権者に配当します。
法人の破産手続きの流れ
法人の破産手続きの大まかな流れは以下の通りです。
弁護士への依頼
法人の破産手続きは通常、弁護士に依頼します。法律上は自力でもできますが、専門家である弁護士に相談をした上で、生活の立て直しや新たな事業の準備、再就職などを優先しましょう。
破産手続きの申し立て
裁判所に破産を申し立てます。申し立てから手続きが始まるまで、しばらく時間がかかることを認識しておきましょう。裁判所の混雑状況によっても変わりますが、数週間から1カ月程度はかかるケースが多いです。
債務者審尋
裁判官から、事業内容や破産申し立ての経緯などの聞き取りが行われます。
破産手続き開始・破産管財人選任
破産管財人に対して、財産の状況などを説明しなければなりません。破産管財人の指示に従い、面談や資料の用意をしましょう。
財産の換価処分
破産管財人が会社の財産を調査し、必要に応じて換価処分し、債権者に配当するための資金を確保します。資産が多かったり、換価しにくい財産があったりする場合、数カ月かかることもあります。
債権者集会
破産管財人が債権者に対して、財産の換価処分状況や配当の見通しなどを説明します。複数回開催されることもあります。破産者および破産管財人の出席は原則義務ですが、債権者は欠席可能です。
配当
債権額に応じて、債権者に配当が行われます。
手続き終結の決定
手続きが終結すると法人格は消滅し、登記簿からも抹消されます。
自己破産手続きを進めるケースも
通常、法人が破産しても経営者個人が支払いの責任を負うことはありません。ただし、経営者個人が企業の連帯保証人となっている場合は、支払義務が課せられます。特に中小企業では経営者が連帯保証人となっているケースも多く、その場合支払いを逃れるために個人でも自己破産手続きをすることもあります。
自己破産手続きをしても新たに会社を設立できますが、融資に悪影響が出る可能性があることを認識しておきましょう。
まとめ
企業が振り出した手形や小切手の支払いができなくなることを、不渡りといいます。不渡りには3種類あり、中でも当座預金残高の不足などが原因で起こる1号不渡りは企業の経営に大きな悪影響を与えるものです。6カ月の間に2回1号不渡りを出すと銀行との取引を行えなくなり、実質的な倒産状態に追い込まれてしまうでしょう。
不渡りを回避する手段には過振りや手形のジャンプなどがありますが、おすすめはファクタリングの利用です。ファクタリングは売掛債権を売却する資金調達方法で、支払期日よりも前に現金を得られます。
株式会社Mentor Capitaは、最短即日で現金化できるファクタリングサービスを提供しています。92%の高い審査通過率と、年間取引件数3,000件以上の実績が特長の一つです。他社で断られた方や赤字・債務超過がある方でも利用できる可能性があるため、まずはお気軽にご相談ください。