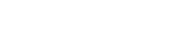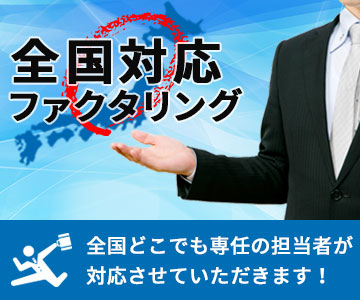事業資金の調達先と金利相場は? 融資の金利をなるべく抑える方法もご紹介
最終更新日:2025年07月31日
融資で資金調達をする際に気になるのが、金利の高さです。金利は低い方が望ましいですが、数ある資金調達手段の中から低金利で利用しやすいものを選ぶのは簡単ではありません。
そこで本記事では、法人が使えるさまざまな資金調達手段の金利相場と、大まかな仕組みを解説します。また、金利をなるべく低く抑える方法も併せてご紹介します。事業資金の調達先を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
Table of Contents
事業資金の調達先と金利相場
事業資金を確保する上で気になるのが調達コストです。調達コストは融資の場合は金利、資産の売買ならば売却手数料という形でかかってきます。一般的な企業が使える資金調達手段の金利(手数料)相場は、以下の通りです。
| 資金調達方法 | 金利(手数料)の相場 |
| 銀行融資(プロパー融資) | 年利1.0~3.0% |
| 銀行融資(信用保証付融資) | 年利1.5~3.0% |
| 日本政策金融公庫からの融資 | 年利1.0~3.0% |
| 不動産担保ローン | 年利2.0~11.0% |
| ビジネスローン | 年利2.0~18.0% |
| ファクタリング | 2社間ファクタリング:8.0~18.0%3社間ファクタリング:2.0~9.0% |
上記はあくまで相場であり、必ずしも表の範囲内に収まるわけではありません。参考程度に認識してください。
なお、調達コストは低いに越したことはありませんが、調達コストが低い手段は審査が厳しくなりやすい点には注意が必要です。ここからはそれぞれの資金調達方法について、詳しくご紹介します。
銀行融資(プロパー融資)
銀行融資は、大きくプロパー融資と信用保証付融資に分けられます。プロパー融資とは、銀行が自己責任のもとで直接利用者に貸し出しを行う仕組みです。貸倒れが発生した際には銀行が損失を背負うことになるため、審査は後述する信用保証付融資と比べると厳しいです。また、担保や保証人が求められることもあります。
一方で、金利相場は比較的低めで、保証料も発生しません。また、信用保証付融資と比べると弁済期間や金利、融資額などの面で融通が利くため、現時点ですでに十分な信用度がある企業が大きな借り入れをする手段として適しています。
プロパー融資を受けたい場合は、事前に十分な経営・弁済実績を作っておきましょう。継続的に黒字を出し、資金繰りを安定させ、他の金融機関への弁済を滞りなく行っていけば、銀行からの信用を獲得できるでしょう。
金利相場
プロパー融資の金利相場は1.0~3.0%程度です。今回ご紹介している資金調達手段の中では低い方ですが、それに見合った高い信用力が求められます。
銀行融資(信用保証付融資)
信用保証付融資は、銀行融資に信用保証協会の保証が付いたものです。信用保証協会は、利用者が債務を弁済できなくなったときに支払いを立て替える機関です。あくまで立て替えなので、利用者は信用保証協会に支払いを行わなければなりません。
信用保証付融資はプロパー融資と比べて、銀行の負う貸倒れリスクが格段に下がります。そのため、プロパー融資の利用が難しい創業直後の企業や中小企業でも比較的利用しやすいです。
ただし、信用保証付融資を受ける際には、信用保証協会に保証料を支払う必要があります。融資自体にかかる金利はプロパー融資とあまり変わりませんが、保証料がかかる分トータルの調達コストは高くなります。
金利相場
信用保証付融資の金利相場は1.5~3.0%です。ただし、それとは別に0.45~1.90%程度の保証料がかかります。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、一般の金融機関が行う金融の補完を目的に設立された、日本政府が100%出資する金融機関です。主に以下の3つの事業を行っています。
・国民生活事業:主に創業・スタートアップ企業や小規模事業者に融資を行う
・農林水産事業:農林水産事業の担い手を育てる事業者向けの融資などを行う
・中小企業事業:中小企業への長期融資、証券化支援などを行う
日本政策金融公庫のメリットは、中小企業でも利用しやすいことです。銀行など民間の金融機関では借り入れが難しい場合でも、日本政策金融公庫なら融資が受けられるかもしれません。また、日本政策金融公庫からの借り入れを予定通り支払えば信用力が高まり、将来別の金融機関で融資を受ける際に有利になります。金利も低く、担保や保証人が必要ない融資も用意されています。
ただし、中小企業事業の融資では、前倒しでまとまった金額を支払うことができません。早期の支払いを視野に入れている場合は、他の資金調達手段を選ぶのも一つの方法です。
金利相場
日本政策金融公庫の金利は、1.0~3.0%程度です。3つの事業ごとに金利が異なり、さらに同じ事業間でも担保の有無や貸付期間によって金利が変わります。なお、審査で特定の条件を満たした場合、通常よりも低い特別利率が採用されます。
不動産担保ローン
不動産担保ローンとは、土地や建物などの不動産を担保とするローンのことです。金融機関は不動産に抵当権を設定し、利用者が支払えなくなった場合はその不動産を売却します。融資限度額は担保の評価額に掛け目(担保評価の掛け率)を掛けた金額となるのが一般的で、通常約60~80%の範囲で設定されます。例えば評価額が5,000万円の場合、融資限度額は約3,000万~4,000万円です。
担保にする不動産は土地や建物ならば何でもよいわけではなく、一定の価値がある(お金に換えられる)ものに限られます。また、一部の不動産担保ローンでは承諾が得られれば、共同経営者など他人が保有する不動産も担保にできます。ただし、ほとんどの場合は不動産の所有者が連帯保証人となるため、事業と無関係な不動産を担保にすることはハイリスクといえるでしょう。
不動産担保ローンは担保がある分、無担保ローンと比べると金利が低くなることが多いです。また弁済期間が長く、利用限度額を大きく取りやすいため、まとまった資金を調達する手段として優秀です。
一方で、弁済が不可能になった場合には担保にした不動産を失うという大きなデメリットもあります。完済して抵当権を解除するまではリスクを背負っていることを認識しておきましょう。
なお、担保にできる不動産は金銭的な価値があるもの、換金性の高いものに限られます。例えば法律上の利用制限が厳しい農地や保安林、あるいは価値の乏しい過疎地の建物、極端に古い建物などは担保にならないことがあります。
金利相場
不動産担保ローンの金利相場は、2.0~11.0%程度です。基本的には、銀行系不動産担保ローンの方がノンバンク系よりも金利が低めです。ただし、不動産の担保としての価値や信用情報、掛け目などにも左右されます。
なお、不動産担保ローンの金利には、変動金利と固定金利があります。変動金利の場合、借り入れ当初の金利は低めに設定されているケースが多いです。ただし、定期的に金利が見直されるため、市場金利の上昇によっては弁済総額が固定金利よりも多くなる可能性があります。
固定金利の場合、借入期間中の金利が一定で、金利の見直しはありません。一般的に変動金利よりも当初の金利は高めですが、将来的な金利上昇の影響を受けないため、支払い計画を立てやすいです。
ビジネスローン
ビジネスローンは、法人や個人事業主が利用できる事業資金専用のローンです。提供元はクレジットカード会社、銀行、消費者金融などです。調達した資金は事業の立ち上げや設備投資、仕入れなどに利用でき、事業を営んでいない個人は利用できません。
ビジネスローンのメリットとして、総量規制の対象にならないことが挙げられます。総量規制は、貸金業者が個人に対して行う融資総額の上限を年収の3分の1までとする規制です。例えば年収600万円の人の場合、融資金額の上限は200万円となります。銀行は貸金業者ではないので総量規制の対象外ですが、似たような自主規制を設けていることが多いです。
総量規制は個人が対象であり、事業を営む法人や個人事業主は対象になりません。そのため、適切な事業・資金・弁済計画があれば年収の3分の1を上回る借り入れができます。
また、ビジネスローンの多くは無担保・無保証人で利用できます。信用力の低い創業間もない企業や中小企業にとっては、使いやすいローンです。
一方で、金利は日本政策金融公庫の融資や銀行融資と比べると高めです。下限金利は低いですが、十分な実績がなければ適用されません。融資上限額も低い傾向にあり、大規模な借り入れには向きません。
金利相場
ビジネスローンの金利相場は、銀行なら2.0~14.0%程度、ノンバンクなら3.0~18.0%程度です。銀行の方が金利が低いですが、審査も厳しめです。条件によって金利は変動しますが、初回の借り入れで下限に近い金利が適用されることは少ないでしょう。
ファクタリング
ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらう資金調達方法です。融資ではなく債権の売買であるため金利はかかりませんが、代わりに買取手数料が発生します。手数料は「債権の額面金額に対して○%」という形でかかるため、額面金額が大きくなるほど手数料も高額になります。
ファクタリングのメリットは、売掛債権の支払期日前に現金を用意できることです。審査も融資と比べると易しめで、自社の経営状態はそこまで深く問われません。また融資ではないので担保や保証人も不要です。
一方で、手数料は銀行融資の利息と比べると高めです。さらに、売掛債権を売却する仕組みであるため、売掛債権の額面金額以上の資金は調達できません。
ファクタリングの中でも、自社とファクタリング会社の2社で行う契約を2社間ファクタリングといいます。2社間ファクタリングでは、取引先(売掛先)は契約に関与しません。取引先の承諾が必要ないため審査がスピーディで、場合によっては申し込んだ即日に入金されることもあります。取引先に知られるリスクも低く、経営難を疑われることはまずありません。
ただし、取引先が関与しないため、ファクタリング会社は債権の存在を直接確認できません。その分ファクタリング会社の背負うリスクが大きくなるため、手数料は後述する3社間ファクタリングと比べると高くなりがちです。
3社間ファクタリングは、自社とファクタリング会社、取引先の3社が契約する仕組みです。取引先の承諾がなければ利用できず、また入金までにやや時間がかかるという欠点があります。一方で、ファクタリング会社が債権の存在を確認できる分、手数料は2社間ファクタリングと比べると低くなることが多いです。
金利相場
先述した通り、ファクタリングに金利はありませんが、代わりに手数料がかかります。手数料は2社間ファクタリングが8.0~18.0%程度、3社間ファクタリングは2.0~9.0%程度です。手数料は、主に取引先の経営状態に左右されます。取引先の信用度が高ければ手数料は低くなりますが、逆に信用度がない場合は審査に落ちる可能性もあります。
融資の金利はどうやって決められる?
融資の金利は金融商品ごとに異なります。また、同じ金融商品でも借りる側の条件や信用度によって金利が変動します。金融機関はどのような要素を確認して、金利を決めているのでしょうか。ここからは、金利が決まる主なポイントについてご紹介します。
融資の期間
金利は一般的に短期的な融資では低く、支払い期間が長くなるほど高くなる傾向にあります。長期になるほど、期間中に企業の経営状況や市場が悪化し、支払いができなくなる可能性が高まるからです。そのリスクを穴埋めするために、金融機関は長期融資の金利を高く設定します。
しかし、常に短期融資で借りるのが最善とは限りません。弁済期間を短くすれば確かに金利は低くなり総支払利息も抑えられますが、1回当たりの弁済額は高くなってしまいます。利息を抑えようとして弁済期間を短く設定し過ぎた結果、月々の負担が増え、資金繰りが悪化してしまっては本末転倒です。
なお、弁済期間は、金融機関による審査の結果に基づいて設定されます。
担保の有無
金融機関が提供するローンには、担保が不要なもの(無担保ローン)と必要なもの(有担保ローン)があります。担保は大きく、物的担保と人的担保に分けられます。物的担保は文字通り「物」です。代表的なのは先述した不動産ですが、ローンによっては預貯金や債権、有価証券、車両なども担保にできます。人的担保は連帯保証人などです。
担保の存在は金融機関側のリスクを減らすため、基本的には有担保ローンの方が金利は低くなりやすいです。ただし、担保の質が低い(換金性に乏しい)場合は金利やその他の条件面で不利になることもあります。
事業計画書
事業計画書とは、事業内容や戦略、業績予測などをまとめた書類のことを指します。経営者の頭の中に存在するアイデアや計画を、具体的な数字や文章を用いて第三者にも分かる形で示せば、金利などの条件面で有利になりやすいです。逆に事業計画書の内容が曖昧だと、審査で不利になります。
事業計画書に決まったルールやテンプレートはありませんが、一般的に記入すべき項目がいくつかあるので把握しておきましょう。初めて事業計画書を作成するときは、日本政策金融公庫の「各種書式」やTOKYO創業ステーションの「事業計画書」などのテンプレートを利用するとよいでしょう。
事業計画書に記載すべき主な内容は、以下の通りです。
| 事業計画書に記載すべき主な内容 | 詳細 |
| 企業概要 | 会社説明や代表者の経歴、事業の目的などを記載する |
| 事業内容 | 事業のビジョンや目標、ターゲット、商品の提供方法などを記載する |
| 市場動向 | 業界の動向や競合分析などを記載する |
| 体制・人員計画 | 役員や従業員の人数などを記載する |
| 資金調達計画 | 資金をどのように集めるかを記載する。 |
| 売上・損益計画 | 売上高や経費の見込額を予測して記載する |
| 実行スケジュール | 売上・損益計画を誰がいつどのように進めていくかをまとめる |
信用度
信用度とは、事業者の支払い能力のことです。例えば創業からの継続年数が長く、財務状況が良好で、借り入れ状況にも問題がない企業は信用度が高いと見なされ、通常よりも低い金利で借りられる可能性が高くなります。逆に創業から間もなかったり、赤字が続いていたりすれば、金利が高くなる他、万が一の場合は審査に落ちるかもしれません。企業の信用度はすぐに獲得できるものでもないため、地道な経営が求められます。
融資の金利の計算方法
融資を受けた後は、元金と利息を支払います。利息は、以下の計算式で求めてください。
利息 = 元金(借入残高) × 借入金利(年利)÷(365日×弁済日数)
例えば、借入金額が100万円、借入金利が10%、借入期間が365日(1年)の場合、1年後に支払う利息は10万円です。計算式は以下の通りです。
100万円 × 10% ÷ 365 × 365 = 10万円
分割で元金と利息を支払う場合、弁済が進むにつれて元金の残高が減るため、それに伴い利息も徐々に減少します。特に、元金を支払う額が一定であれば、利息が減る分だけ総弁済額も回を追うごとに少なくなります。
日本貸金業協会や日本政策金融公庫などでは、毎月の弁済額をシミュレーションできるWebページを公開しているので、借り入れ前に計算しておくとよいでしょう。
日本貸金業協会 シミュレーション
日本政策金融公庫 事業資金用 返済シミュレーション
支払い方法によっても金利の額は異なる
融資の支払い方法には、「元利均等」と「元金均等」があります。
元利均等は、毎回の支払額(元金+利息)が一定になる仕組みです。最初のうちは支払いに占める利息の割合が多く、その後徐々に元金の割合が増えていきますが、毎回の支払額は常に一定になります。毎回の支払額が変わらないため弁済計画が立てやすく、開始当初の弁済額を少なくできるのがメリットです。一方で、同じ借入期間の場合、元金均等と比べて総弁済額は多くなります。
元金均等は毎回の弁済額のうち元金が一定で、元金に応じて利息が変化する仕組みです。最初のうちは元金が多いので利息も多くなりますが、支払いが進めば利息は減っていきます。
開始当初の弁済額が多くなるため借り入れ直後は負担が大きいですが、弁済が進むにつれて1回当たりの弁済額は減ります。また元利均等と比べると元金が早く減るため、借入期間が同じならば元利均等よりも総弁済額が少なくなるのもメリットです。
支払い回数によっても金利の支払総額は異なる
元金と利息の支払いは、必ずしも月1回行うとは限りません。条件次第で年4回や年1回になることもあります。同じ金額、同じ金利、同じ期間で借りても、支払い回数が違えば総支払利息は変わります。例えば、120万円を年利5%で借り入れ、元金均等で1年間で弁済する場合を考えてみましょう。この場合、支払い回数が年1回、年4回、年12回(月1回)の総支払利息はそれぞれ以下のようになります(日本政策金融公庫のシミュレーターで試算した場合)。
| 支払い回数 | 総支払利息 |
| 年1回 | 60,000円 |
| 年4回 | 37,500円 |
| 年12回 | 32,500円 |
上記の表からも分かる通り、支払い回数を増やすと総支払利息は減ります。これは細かく支払うほど、元金が少なくなる機会が増えるためです。ただし、支払い回数が増えると手元の現金が減るため、キャッシュフローに余裕が生まれにくくなります。総支払利息とキャッシュフローのバランスをどのように取るかが大切です。
融資の金利をなるべく抑える方法
融資の金利は低いに越したことはありませんが、最終的に金利を決めるのは金融機関です。ここからは、金融機関から高い評価を得て、低い金利を提示してもらうための手法をご紹介します。
業績が良いときに融資を申し込む
企業の業績は常に一定ではなく、景気や市場動向、企業内文化の変化などに左右されます。業績が良い時期に融資を申し込めば、それだけ金融機関からの評価を得られるでしょう。逆に業績が悪い時期に申し込むと、金利が高くなったりそもそも審査に落ちたりする可能性が高まります。
審査の際には過去数年分の損益計算書や貸借対照表などの提出を求められることが多いため、対象となる期間の業績の良し悪しには十分気を付けましょう。
複数の借り入れ方法や借入先を比較検討する
金融機関ごとに金利を決める基準は異なります。例えばある金融機関で年利10%を提示されたからといって、別の金融機関でも必ず10%になるとは限りません。複数の借り入れ方法や借入先を比較すれば、低金利な融資にたどり着ける可能性は高まります。
ただし、複数の銀行の信用保証付融資を同時に申し込むのはおすすめできません。信用保証協会は共通であり、同時に申し込みをした事実は協会側にすぐに把握されます。同時に複数の銀行で信用保証付融資は受けられない上に、民間金融機関を2つ使う理由もありません。
日本政策金融公庫と銀行の同時申請は可能ですが、こちらもあまりおすすめできません。両者を利用したい場合はまず金利が低くなりやすい日本政策金融公庫に申し込み、希望した額に届かなかった分を銀行で借りるという流れがよいでしょう。
担保や保証人を用意する
担保や保証人の用意ができていれば金融機関の貸倒れリスクが下がるため、金利を低くしてもらえるかもしれません。もちろん、支払いができなくなれば担保を失うリスクはありますが、支払いの見通しが立っている場合は、有利な条件での借り入れの手段として検討してみてもよいでしょう。なお、不動産を担保にしても、実際に物件を提供するわけではないため、債務者側は不動産を利用し続けられます。
担保にできる不動産がない場合は、ABL(売掛債権担保融資・動的担保融資)の利用も考えてみてください。売掛債権や動産(機械設備や在庫など)を担保にできるため、中小企業でも比較的利用しやすいです。
綿密に事業計画書を作成する
事業計画書の内容は、融資の可否や適用金利に大きな影響を与えます。たとえ財務諸表が平凡であっても、事業計画に説得力があり、将来の成長可能性が高いと評価されれば、より有利な金利で融資を受けられることがあります。
優れた事業計画書を作成するためのコツはさまざまありますが、その中でも大切なのは複数の視点からバランスよく計画を組み立てることです。技術面や営業面など、特定の分野に偏った計画書は説得力に欠け、評価されにくくなる傾向があります。
事業計画書では、自社の強みだけではなく弱みや課題なども明確にしておきましょう。改善すべき点が把握・提示できていれば、自社を客観的に分析できている企業として評価されやすくなります。
なお、金融機関によっては事業計画書のテンプレートを用意してくれていることがあります。その場合はテンプレートに従って書き進めましょう。
まとめ
事業資金の調達方法は複数あり、それぞれ調達コスト(金利や手数料)が異なります。基本的には、調達コストが低い資金調達方法ほど審査が厳しくなりやすいです。また、金利は金融機関の種類だけではなく、支払い期間や担保の有無、事業計画書の内容などにも左右されます。
なるべく低金利で融資を受けたいのならば、業績が良いときに申し込む、複数の借り入れ方法を検討するといった工夫をしましょう。
融資のハードルが高いと感じたときは、ファクタリングの利用も検討するのがおすすめです。融資と比べると審査に通りやすく、2社間ファクタリングなら最短即日で入金が受けられるケースもあります。
株式会社 Mentor Capitalは、年間3,000件以上の取引実績があるファクタリング会社です。審査通過率は92%(2023年1月~2023年12月の実績)と高く、赤字や債務超過でも利用できるケースがあります。業種別に適切なプランをご提案しますので、お気軽にご相談ください。