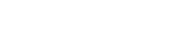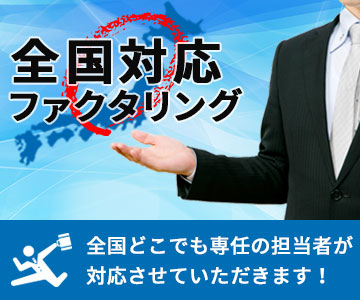ファクタリングに利息制限法は適用される? 利用時にかかる手数料や例外となるケースを紹介
最終更新日:2025年09月10日
ファクタリングは貸し付けではないので利息は発生せず、一部の例外的な事例を除いて利息制限法は適用されません。代わりに手数料がかかりますが、手数料の上限を具体的に定めた規制はありません。また貸金業登録をしていないファクタリング会社が、実質的に貸し付けと見なされる業務を行うのは違法行為です。
本記事では、利息制限法の概要やファクタリングの手数料を決める主な要素、例外的にファクタリングが利息制限法の対象となるケースなどについて解説します。ファクタリングの利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
Table of Contents
利息制限法とは?
利息制限法とは、金銭の貸し借りをした際に発生する利息や遅延損害金を決める金利の上限を定めた法律です。消費者金融などの法人が行う貸し付けだけではなく、個人間(家族・友人間など)での金銭の貸し借りにも適用されます。仮に利息制限法の上限を超える金利で契約しても、超過分は無効となります。利息制限法による金利上限は、以下の通りです(※)。
| 元本 | 利息制限法による金利上限 |
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
利息制限法では、元本の額によって金利の上限が異なります。貸し手から見れば、元本額が少ないほど高い金利を取れることになります。
以前は、例えば120万円を貸す際に、金利が15%となる元本120万円での貸し付けを行わず、元本60万円ずつで2回に分けて、金利を18%取ろうとする業者も存在しました。しかし現在は、同じ人が同じ貸し手から複数回貸し付けを受ける場合、元本の合計額を基準として金利を定める必要があり、このような抜け道は使えなくなっています。
利息制限法以外の金融取引に関する法律
貸し付けなどの金融取引は、利息制限法の他にも複数の法律で規制されています。ここでは代表的な法規制である、貸金業法と出資法の概要について解説します。
貸金業法
貸金業法は、金銭の貸し付けを事業とする貸金業者の事業を規制し、適正な貸金業務を行わせるための法律です。通常、個人間でのお金の貸し借りは貸金業法の対象外ですが、貸す人が反復継続する意思を持って貸し付けを行う場合は規制の対象になり得ます。貸金業法の主な内容は、以下の通りです(※)。
| 規制の種類 | 各規制の概要 |
| 登録制度 | 貸金業者は内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受け、3年ごとに更新を行わなければならない |
| 総量規制 | 借入残高が本人の年収の3分の1を超える貸し付けを制限する規制貸金業者ではない銀行からの借り入れは対象外住宅ローンなど一部の貸し付けは、貸金業者が行うものでも対象にならないことがある |
| 取り立ての規制 | 正当な理由がなく、午後9時~午前8時の間に取り立てを行うなどの行為が制限されている違法な取り立てを受けた場合は、弁護士や日本貸金業協会に相談するのがよい |
出資法
出資法は、出資や貸し付けの金利を規制する法律です。利息制限法と同じく、金利の上限を定めています。利息制限法と出資法それぞれの金利上限は、以下の通りです(※)。
| 業者の貸し付け | 個人間の貸し付け | |
| 利息制限法 | 15~20% | 15~20% |
| 出資法 | 20%(かつては29.2%) | 109.5% |
利息制限法の制限を超えた場合、超過分の金利は無効で、さらに行政処分の対象となります。一方、出資法の制限を超えた場合は、刑事罰の対象となります。
かつては利息制限法と出資法の上限金利に差があり、間の金利帯はグレーゾーン金利と呼ばれていました。当時は一定の要件を満たせばグレーゾーン金利でも有効になることがありましたが、現在は利息制限法を超過すれば行政処分の対象となります。
※参考:e-gov法律検索.「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」.
ファクタリングに利息制限法は適用される?
ファクタリングに利息制限法は適用されません。理由は明確で、ファクタリングは売掛債権を買い取る仕組みであり、利息が発生する金銭の貸し付けではないからです。同じ理由で、貸金業法や出資法も適用されません。一方でファクタリングでは手数料がかかりますが、これは利息ではないため、ファクタリング会社側が自由に設定可能です。
ただし、買戻特約(債務不履行になった場合に利用者が債権を買い戻す特約)がある場合などの一部のケースでは、例外的に利息制限法の対象となります。
ファクタリングを利用する際は手数料がかかる
先述した通り、ファクタリングには利息はありません。代わりに手数料がかかります。ここからは、ファクタリングの手数料の相場と注意点をご紹介します。
手数料の相場
ファクタリングを利用する際の手数料の相場は、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで異なります。それぞれの相場は、以下の通りです。
| ファクタリングの種類 | 手数料の相場 |
| 2社間ファクタリング | 売掛債権額の8~18% |
| 3社間ファクタリング | 売掛債権額の1~9% |
2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社が契約する仕組みです。売掛先に知られずに利用でき入金スピードも速いですが、手数料は高くなる傾向にあります。3社間ファクタリングは利用者とファクタリング会社と売掛先が契約する仕組みで、売掛先の承諾が必要になりますが、手数料は低くなる傾向にあります。
手数料には上限がないので事前に確認しておく
貸し付けの際の金利が利息制限法や出資法で規制されているのに対して、ファクタリングの手数料にはそうした規制がありません。
例外的に、あまりにも高過ぎる場合は、民法上の一般原則である「公序良俗違反」によって無効になるケースがあります。ただし、無効にできない可能性もある上に、仮に無効にできるとしても手間がかかります。
手数料の目安を知るためにも、契約前に複数のファクタリング会社から見積もりを取りましょう。手数料が他社と比べて極端に高い業者との契約は、避けるようにしてください。
ファクタリングの手数料を決める主な要素
ファクタリングの手数料の相場は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで異なりますが、それ以外にも手数料を決める要素がいくつかあります。手数料を決める主な要素について、見ていきましょう。
売掛先の信用度
ファクタリングの審査では、売掛先の信用力が重視されます。ファクタリングは売掛債権を譲渡する仕組みなので、自社に赤字や債務超過といった問題があっても、売掛先に十分な支払い能力があれば手数料が低くなる傾向にあります。
逆に自社の経営が健全であっても、倒産の危機にある場合などは手数料が割高になったり、契約自体を断られたりする可能性があるでしょう。
契約形態の種類
先述した通り、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは手数料の相場が異なります。
2社間ファクタリングの方が手数料が高いのは、ファクタリング会社の背負うリスクが大きいためです。2社間ファクタリングでは、売掛先が契約に関わりません。例えば、利用者が架空債権の計上や二重譲渡(1つの売掛債権を複数社に譲渡すること)をしても、ファクタリング会社側は気付けないリスクがあります。ファクタリング会社は大きなリスクを背負うことになる分、手数料を高めに設定しているのです。
一方、3社間ファクタリングの場合は売掛先が契約に関与するため、架空債権の計上や二重譲渡が行われていた場合でも譲渡代金を引き渡す前に発覚します。そのため、3社間ファクタリングは手数料が低く抑えられるのです。
売掛債権の金額
売掛債権の金額が高くなるほど、手数料が低くなる傾向にあります。ファクタリング会社の利益は、得た手数料から人件費などの経費を差し引いた金額になりますが、経費は売掛債権の額が大きくても小さくてもあまり変わりません。そのため売掛債権の額面金額が多ければ、効率的に多くの利益を得られます。
ただし、金額が大きくても売掛先の信頼性が低い場合は、手数料が高くなる可能性もあることを認識しておきましょう。
ファクタリングの利用実績
ファクタリングの利用実績が豊富にあれば、手数料が低くなるかもしれません。ファクタリング会社からすれば、初見の利用者よりも、売掛先から受け取った売掛金を支払ってくれた実績がある継続的な利用者の方が安心して契約しやすいです。ただし、ファクタリングの継続的な利用は経費の増大にもつながるため、過剰な利用は避けましょう。
支払いまでの期間
売掛債権が実際に支払われるまでの日数が長くなると、手数料は高くなる傾向にあります。例えば、支払期日が30日後の売掛債権と180日後の売掛債権では、後者の方が手数料が高くなりやすいです。
支払いまでの期間が長くなるほど、不測の事態が発生して売掛先の支払い能力が失われる可能性が高くなるためです。
ファクタリングで例外的に利息制限法が適用されるケース
基本的にファクタリングでは利息制限法が適用されませんが、貸金業と見なされる事業を行っている場合は、例外的に適用されます。
買戻特約や償還請求権がある
買戻特約は、売掛先が債務を履行できなくなった場合に利用者が売掛債権を買い戻す契約条項です。買戻特約が適用された場合、売掛債権が利用者の元に戻ってくるため、回収は利用者が自ら行わなければいけません。この場合、ファクタリング会社は売掛金の未回収リスクを負っておらず、実質的に貸し付けをしていると見なされるため、利息制限法が適用される可能性があります。
償還請求権は、売掛先が債務を履行できなくなった場合に、ファクタリング会社が利用者に支払いを求める権利です。この場合もファクタリング会社は実質的に貸し付けを行っていると見なされ、利息制限法が適用されることがあります。
契約を結ぶ前に、買戻特約も償還請求権の有無を含めて契約書の内容を確認してください。
引当財産が利用企業の財産とされている
引当財産とは、売掛先が債務を履行できなくなった場合に、ファクタリング会社が取り立ての対象にする財産です。貸し付けの担保のようなものです。
通常、ファクタリング契約では引当財産は設定されませんが、一部のファクタリング会社は引当財産の仕組みを採用しているケースがあります。この場合ファクタリング会社は実質的に売掛金の未回収リスクを負っておらず、利息制限法の対象となることがあります。
給与ファクタリングである
給与ファクタリングとは、労働者の給与債権(給与を受け取る権利)を譲渡するファクタリングです。給与ファクタリングは形式上は通常のファクタリングと同じ債権譲渡ですが、実質的には労働者に貸し付けを行い、将来の給与で支払わせる仕組みになっています。そのため、通常給与ファクタリングは貸金業と見なされ、利息制限法が適用されます。
給与ファクタリングの仕組み自体は違法ではありませんが、事業として実施する際には貸金業登録が必要です。貸金業登録を行っていない事業者の給与ファクタリングは違法行為であり、金融庁も注意喚起しています。貸金業の登録を行っている事業者の給与ファクタリングを利用することはおすすめしません。高い手数料を支払い続けることになってしまい、自転車操業に陥る可能性があるためです。
なお、ファクタリングサービスを提供している株式会社Mentor Capitalは、給与ファクタリングを行っておりません。
※参考:金融庁.「給与の買取をうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」.
貸金業には利息制限法が適用される
業者がファクタリング会社を名乗っていても、実質的に貸し付けと見なされる行為を行っている場合は、貸金業者に分類されます。先述した通り、貸金業者は貸金業の登録を受けなければならない上に、利息制限法の対象にもなります。買戻特約や引当財産の設定をしているにもかかわらず、貸金業登録をしていない業者は違法業者の可能性が高いため、契約しないようにしましょう。
万が一契約してしまった場合は、弁護士や警察、日本貸金業協会などに相談してください。
まとめ
利息制限法は、金銭の貸し借りの際に発生する金利を制限する法律です。金利は貸し付ける金額によって変動し、金利上限を超えた分は無効になります。他にも、貸金業者は貸金業法や出資法などによって規制されます。
ファクタリングは貸し付けではないので利息制限法の対象にはならず、利息も発生しません。その代わり売掛債権の額面金額に応じた手数料が生じます。手数料は、売掛先の信用度や契約形態の種類、売掛債権の額面金額などによって決まるケースが多いです。手数料が高過ぎるファクタリング会社と契約してしまわないように、複数社に見積もりを依頼しましょう。
なお、買戻特約や引当財産の設定などがあるファクタリングは実質的に貸し付けと見なされ、利息制限法の対象となることがあります。貸し付けに該当する業務を貸金業登録していない業者が行うのは違法行為となるため、契約内容をしっかり確認してください。
ファクタリングを検討している場合は、株式会社Mentor Capitalがおすすめです。法人・個人問わず、業種ごとに適したプランをご紹介いたします(給与ファクタリングは行っておりません)。赤字や税金滞納がある方にも対応しているので、まずは一度ご相談ください。