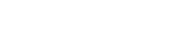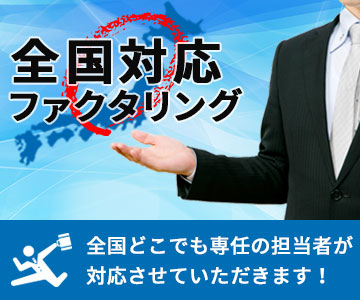売掛債権とは? 種類や仕組み、未回収リスクを避けるためのポイントを解説
最終更新日:2025年07月31日
企業が商品やサービスを提供した対価としての代金を回収する権利のことを、売掛債権といいます。企業間取引の多くは売掛債権を用いた掛取引で行われるため、経営者や経理担当者は売掛債権の仕組みを十分に把握しておくことが必要です。知識がないまま、取引を行っていると資金不足や倒産につながるかもしれません。
そこで本記事では、売掛債権の種類や仕組み、未回収リスクを避けるためのポイントなどを解説します。安定した経営を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
Table of Contents
売掛債権とは?
売掛債権とは、掛取引によって発生した代金を受け取る権利のことです。掛取引は、売り手企業がサービスや商品を先に提供し、買い手企業が支払期日までにその対価となる代金を支払う仕組みです。一定期間内の取引をまとめて精算でき、現金払いと比べて各種書類の発行や請求の回数を削減できるため、企業間取引の場で広く採用されています。
売掛債権は、会計上は流動資産と見なされ、比較的短期間のうちに現金化可能です。ただし、売掛債権には時効があります。時効は契約形態により異なりますが、通常は権利を行使できると知ったときから5年、もしくは権利を行使できるときから10年です。権利を行使しなかった場合、売掛債権は消滅します。
売掛債権の種類
売掛債権には「売掛金」「受取手形」「電子記録債権」があります。いずれも後で代金を受け取れる権利という点では共通していますが、まったく同じものではありません。ここからは、それぞれについて詳しくご紹介します。
売掛金
売掛金は、一般的には受取手形にも電子記録債権にも該当しない売掛債権です。公的な証書は発行されず、請求書などを元にして取引が行われます。そのため、互いの信頼がなければ成り立ちません。売掛金の支払期日は通常売り手側が提示し、契約書を交わします。
企業同士の取引とはいえ第三者の介入しない約束であり、受取手形や電子記録債権と比べると回収の確実性は低いです。一方で手間が比較的かからないというメリットがあり、卸売業・製造業・サービス業など幅広い業種で活用されています。
受取手形
受取手形とは、約束手形を用いた取引で発生する売掛債権です。約束手形は、期日までに決められた支払いをすると約束したことを証明する有価証券です。
約束手形は振出人(支払う側)と受取人(受け取る側)の双方の合意に基づき、振出人が発行します。振出人は、受取人に約束手形を渡します。受取人が受け取った約束手形が受取手形です。受取人は支払期日直後に銀行に受取手形を持ち込み、現金を受け取ります。
なお、受取手形を現金化できるのは、支払期日から3営業日以内(支払期日当日を含む)です。3営業日を過ぎた場合は、銀行で取り立てられなくなり、振出人に直接請求をしなければなりません。
受取手形は銀行が仲介するため、売掛金と比べると回収の確実性が高いというメリットがあります。また、支払期日前に銀行などの金融機関に手形を買い取ってもらう手形割引の仕組みを使えば、迅速な現金化が可能です。
電子記録債権
電子記録債権は、電子的に記録された売掛債権です。従来の売掛金や約束手形を用いた取引の課題を解決し、中小企業の資金調達を円滑化することを目的に作られた比較的新しい仕組みで、以下のようなメリットがあります。
・電子的な記録なので紛失・盗難・偽造などのリスクが低い
・ペーパーレスな職場を実現できる
・債権の分割譲渡が容易である
電子記録債権を利用する際には、それを管理する電子債権記録機関の窓口金融機関での申し込みが必要です。2025年6月17日時点で電子債権記録機関は5社ありますが、窓口金融機関が多いのは株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)です(※)。
売掛債権の仕組み
売掛債権の時効や回収方法を知っておけば、未回収リスクを減らせます。ここでは、特に知っておきたい売掛債権の仕組みをご紹介します。経営者や経理担当者の方は、押さえておきましょう。
売掛債権の時効
売掛債権の時効期間は、2020年4月の民法改正を境に異なります(※)。改正前(2020年3月以前)に発生した債権については、飲食代金は1年、建築代金は3年など、業種ごとに短期消滅時効が定められていました。
一方、2020年4月以降に発生した債権については業種を問わず、以下の早い方を時効とします。
債権者が権利を行使できることを知ってから、5年間行使しないとき(主観的起算点)
債権者が権利を行使できるようになってから、10年間行使しないとき(客観的起算点)
通常、債権者は債権の発生を知っているため、主観的起算点が該当することが多いです。例えば、2025年5月にサービスを提供し、2025年6月末を支払期日として請求書を発行した場合、2030年6月末が時効となります。なお、後述する手法を使えば、時効を延長させる(新たな起算点を設定する)ことも可能です。
※参考:e-gov法令検索.「民法(明治二十九年法律第八十九号)」.
売掛債権の回収方法
掛取引を行う際には、代金をどのように回収するかも決めておきましょう。
売掛債権の支払いを現金で行うケースもゼロではありませんが、銀行振込で行うことが一般的です。銀行振込の場合、支払期日になったら、指定した口座に入金が行われているかを確認しましょう。支払期日を過ぎても入金が行われない場合はまずはメールや電話で確認を行い、支払意思が見られない場合は法的措置も視野に入れましょう。
受取手形の場合は、支払期日から3営業日以内に銀行に持ち込むか、手数料を支払って手形割引を利用するかの2択です。手形割引は銀行もしくは手形割引専門業者を通じて利用できます。手数料だけで見ると、銀行は安い傾向にあり、手形割引業者は高い傾向がありますが、手形の残存日数や振出人の信用度にも左右されることを認識しておきましょう。
電子記録債権を利用している場合は、自動的に買い手企業の口座から資金が引き落とされ売り手企業の口座に入金されるため、特別な回収業務はありません。
売掛債権という仕組みのメリット
企業間取引の場で売掛債権の仕組み(掛取引)を利用する、主なメリットは以下の3点です。
取引を一括で請求できる
売掛債権の仕組みを導入すれば、取引で生じた代金をまとめて請求できます。例えば、1カ月の間に5回取引をする場合、現金取引だと売り手企業は領収書や請求書を5回発行しなければなりません。一方、掛取引の仕組みを採用すれば、これらの作業は1回で済みます。買い手企業も請求書の受け取りや入金の回数を減らせます。
取引先の幅が広がる
売掛債権の仕組みを利用すれば、取引先を新たに開拓できるかもしれません。
買い手企業から見た場合、現金取引にしか対応していない企業よりも、掛取引に対応してくれる企業の方がありがたい存在です。先述した通り、掛取引であれば取引に伴って発生するさまざまな事務作業を減らせる上に、支払いを先延ばしにできる分資金繰りに余裕を持てるようになるからです。
資金がない場合も取引できる
売掛債権の仕組みは、先に売り手企業が商品やサービスを納品し、後で買い手企業が支払いをするものです。そのため、契約を交わした時点で買い手企業が十分な現金を持っていなくても問題ありません。買い手企業にとっては資金繰りの面で助かり、売り手企業にとっては売り上げを確保できるというメリットがあります。
もちろん、買い手企業が支払期日までに代金を用意できないリスクがあることを、売り手企業側は十分に把握しておかなければなりません。
売掛債権という仕組みのデメリット
売掛債権という仕組みにはさまざまなメリットがある一方で、見逃せないデメリットもあります。特に売り手側は一定のリスクを背負うことになるため、契約内容や取引先の信用力に問題がないか、事前に精査した方がよいでしょう。
キャッシュフローが悪化する可能性がある
売掛債権の仕組みを導入すると、売り手側のキャッシュフローが悪化する可能性があります。キャッシュフローとは、企業に出入りする現金のことです。キャッシュフローのうち、会社に入ってくる現金が「キャッシュ・イン・フロー」、出ていく現金が「キャッシュ・アウト・フロー」です。手元に十分な現金があり、当面の資金ショートリスクが少ない状態を「キャッシュフローに余裕がある」と表現します。
なお、キャッシュフローの話における現金とはいわゆるお札や硬貨などの他に、以下のものを含みます。
要求払預金:事前の通知なし、もしくは数日前の通知で払い戻しができる期限のない預金を指す。普通預金や定期預金が該当する
現金同等物:短期間で容易に現金化でき、かつ価格変動リスクが少ない短期投資のこと。一部の定期預金、譲渡性預金、公社債投資信託などが該当する
余裕のあるキャッシュフローにするためには、売り上げの回収はなるべく早く、支払いは遅くすることが大切です。しかし、売掛債権の仕組みを利用すると、どうしても売り上げの回収が遅くなってしまいます。最悪の場合、会計上は黒字なのに手元の資金が尽きてしまい、手形代金や従業員への給料が支払えず倒産しまうことにもなりかねません。
なお、常にキャッシュフローに一定の余裕がある状態が理想ですが、資金を有効活用できていないと判断され、経営効率の低下につながる可能性があります。必要な運転資金を確保しつつ、余剰資金は投資や借入金の返済などに活用するなど、バランスの取れた資金管理を心掛けましょう。
時効に注意する
先述した通り、売掛債権には時効が存在します。ただし、時効中断措置を取れば、時効を更新できます。売り手企業が使える時効中断措置は、以下の5点です。
| 時効中断措置の種類 | 概要 |
| 民事訴訟を行う | 買い手企業に対して、通常の民事訴訟を起こす。判決が出れば強制執行もできるが、時間がかかる |
| 支払督促を行う | 裁判所が買い手企業に対して督促を行う |
| 民事調停を行う | 裁判所での話し合いによる解決を目指す |
| 債務の承認を行わせる | 債務があることを買い手企業に認めさせる |
| 売掛債権の一部を支払わせる | 売掛債権のうち、一部でも支払わせる |
上記に挙げた5点のうち、民事訴訟や支払督促、民事調停は買い手企業の協力なしでできます。債務の承認と売掛債権の一部支払いは、買い手企業の協力が必要です。
与信管理が必要
与信管理とは、与信(取引相手の支払い能力)を精査し、未回収リスクを抑えるための活動の総称です。適切な与信管理は貸し倒れを防ぎ、企業の存続可能性を高めます。また、他の取引先や金融機関からの信頼獲得にもつながるでしょう。
与信管理のプロセスは主に取引前と取引後に分けられ、以下のような流れで行うことが一般的です。
| 取引前のプロセス | 情報収集(与信調査) | 取引先の経営状態に関する情報を集める。決算書や業界動向、信用調査会社の資料の他、従業員の態度なども判断材料になる |
| 信用力評価 | 与信調査の情報を元に取引先の経営状態を分析し、どれくらいの信用力(支払い能力)があるのか判断する | |
| 与信枠の決定 | 信用力評価を元に、どれくらいの与信枠(売掛金の最大値)を与えるか決める | |
| 契約条件の交渉・契約の締結 | 与信限度額を元に契約条件を交渉し、契約を結ぶ | |
| 取引後のプロセス | 支払いのチェック | 取引後の支払いがスムーズに行われているかを確認する |
| 見直し | 取引開始後も定期的に与信調査を行い、状況に応じて与信枠や契約条件を変更する |
未回収リスクがある
適切な与信管理は非常に大切ですが、どれだけ入念に管理を行っても未回収リスクをゼロにすることはできません。帝国データバンクの発表している資料によれば、2024年度の企業倒産件数は1万70件(前年度8,831件、13.4%増)で、11年ぶりに1万件を超えたとのことです。当然、企業の倒産が増えれば、それだけ売掛債権の未回収リスクも高まります(※)。
売掛債権の仕組みを導入する以上、常に未回収のリスクがついて回ることは理解しておきましょう。
※参考:帝国データバンク.「倒産集計 2024年度報(2024年4月~2025年3月)」.
未回収リスクを避けるためのポイント
売掛債権の未回収リスクをゼロにすることは難しいですが、ある程度低く抑えることはできます。売掛債権の未回収の原因は、主に以下の3つに分けられます。
・自社のミス:自社側に入金確認漏れや経理上のミスなどがある
・取引先のミス:取引先側に入金忘れなどのミスがある
・取引先の経営悪化や踏み倒し:取引先側に支払い能力もしくは支払いの意思がない
特に危険なのが取引先の経営悪化や踏み倒しです。ここからご紹介するような兆候がある取引先の場合、注意した方がよいでしょう。
従業員の離職が多い企業に注意する
従業員の離職が多い企業との取引は、慎重に行いましょう。従業員が次々と辞めていく企業は多くの場合、何らかの問題を抱えている可能性が高いです。例えば多くの従業員が労働条件や労働環境に不満を抱えている、経営状態の悪化に伴うリストラを行っている、希望退職者を募っている、といったことがあるかもしれません。
離職者の多い企業では残った従業員に業務が集中するため職場が疲弊しやすく、士気の低下やトラブルが起こりやすくなります。その結果サービスや商品の質が低下し、売り上げが下がり、支払い能力も失われていくのです。
取引先銀行を変更した企業に注意する
取引先が突然銀行(メインバンク)を変更してきた場合も、注意しましょう。信用力不足で融資を断られ、やむなくより借りやすい別の銀行に変えた可能性があるためです。さらに先述した「従業員の離職が多い」という条件にも当てはまっている場合は、より注意した方がよいでしょう。
ただし、取引先がメインバンクを変更する理由は「融資を断られたから」だとは限りません。単にメインバンクのサービスに不満があっただけかもしれない他、企業の成長に伴い地方銀行からメガバンクに乗り換えた可能性もあります。早計な判断は避け、状況を慎重に見極めることが大切です。
支払条件の変更を打診してきた企業に注意する
取引先から突然支払い条件の変更(先延ばしや分割払いのお願いなど)があった場合は、慎重に対応する必要があります。取引先の目的がキャッシュフロー改善や業務効率化であれば問題ありませんが、何度も申し出がある場合は資金繰りが苦しくなってきている可能性も考えられます。
このような状況では、取引先の重要度や今後の関係性を踏まえた上で対応を検討しつつ、自社の資金繰りに悪影響が及ばないよう注意しましょう。もちろん、取引先の経営状態も忘れずに確認してください。
売掛債権を回収する方法
未回収の売掛債権が発生した場合は、ここからご紹介するプロセスに従って回収を進めましょう。放置すると状況が悪化する可能性が高いため、できるだけ早めに動き出すことが大切です。
契約内容を確認しておく
手元に契約書、見積書、請求書、納品書などをそろえ、契約内容を改めて確認しましょう。まず、自社に何らかの落ち度がないか確認してください。請求書を送り忘れていないか、本当に支払期日が過ぎているのかなどを一通りチェックしましょう。
チェックが終わったら、契約書の「期限の利益喪失条項」を確認します。期限の利益喪失条項とは、債務者の契約違反があった場合に、本来の支払期日よりも前に債務を履行させる仕組みです。これが設けられている場合、契約違反があれば支払いが遅れた売掛債権以外の売掛債権も併せて請求できます。
また、定期的に取引を行っている場合は商品やサービスの提供を一時的にストップさせ、新たな売掛債権が発生するのを防ぎましょう。
取引先の担当者に連絡をする
契約内容を確認し、自社に落ち度がないと確認できたら、取引先に連絡を入れましょう。その際に高圧的な態度を取るのは避けてください。単に失念していたなど、取引先に悪意がなかった場合に、関係性が悪化するリスクを避けるためです。
内容証明郵便で請求書を送付する
内容証明郵便とは、いつ、誰が誰にどのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する制度です。利用すれば請求を行ったことを対外的に証明できます。
内容証明郵便には、紙媒体のものと電子的なもの(e内容証明)があります。紙媒体のものは、一部の郵便局から送付手続きが可能です。送付の際には相手に送る内容文書1通の他、差出人と郵便局が保存する謄本2通を作成します。用紙や記載用具に制限はありません。ただし、1行の文字数や行数の制限があるため、あらかじめマスが印刷されている市販の内容証明書用紙を利用するとよいでしょう。
e内容証明は、インターネット上から送付できます。紙の内容証明より少し安価に利用できます。
内容証明郵便には、期日までに支払が行われない場合に法的手段を取る旨を記載するのが一般的です。法的な手段を取る意思を見せることにより、支払いを促す効果も期待できます。
法的手段を使って回収する
内容証明郵便を送付してもなお相手から支払いが行われない場合は、法的手段に移ります。基本的な手順は以下の通りです。
1.仮差押え
2.訴訟・支払督促
3.強制執行
仮差押えとは、債権を回収する前に取引先が資産を勝手に隠したり売却したりするのを防ぐために、資産を凍結する手続きです。銀行預金や現金の他、不動産、生命保険、自動車、機械、債権などが対象となります。
仮差押えが完了したら、訴訟もしくは支払督促を行います。訴訟は裁判所に支払いを命じてもらうための手続きで、取引先の連帯保証人に対しても請求できるのがメリットです。また、売り手側の裁判所で審理が行われるため、費用や手間を抑えられます。一方で数カ月程度時間がかかる、弁護士費用がかさむなどのデメリットもあることを認識しておきましょう。
支払督促は裁判所から文書で支払いを督促してもらうもので、相手から異議が出なければ訴訟の判決と同じ効力を持ちます。異議が出ない場合は、裁判所に行く必要はありません。
ただし異議が出た場合は訴訟となり、買い手側の裁判所で審理を行います。買い手企業の所在地が遠方の場合は、費用や手間がかかります。支払督促をしても効果がなさそうな場合は、最初から訴訟をした方がよいかもしれません。
和解や勝訴に至っても支払いが行われない場合は、強制執行で相手の財産を差し押さえます。ただし、相手の資産状況によっては、十分な回収ができないこともあります。
キャッシュフローの悪化を防止! 売掛債権の請求方法・資金調達方法
売掛債権を保有している場合は、いくつかの請求方法や資金調達方法があります。場合によっては、売掛債権の支払期日を待つよりも効率的にキャッシュフローを改善できるでしょう。
請求代行
請求代行とは、請求に関する業務の一部、もしくは業務の全てを委託できるサービスです。請求代行を利用すれば、未回収リスクを低減したり、他の業務に投入するリソースを増やしたりできます。
サービスの内容は請求代行業者ごとに異なりますが、主なサービスの内容は以下の通りです。
| サービス内容 | 概要 |
| 請求書の作成・発行 | 提供した商品やサービスに応じた請求書を作成し、取引先に送付する |
| 代金管理・回収・消込 | 取引先から代金を回収し、消込(売掛債権を消すこと)を行う。支払いがない場合は、取引先に督促の連絡を入れる |
| 与信審査 | 取引先の支払い能力を調査し、与信枠を決定する。反社チェックなどを委託できる場合もある |
| 未払い時の保証 | 未払いが発生した場合、売掛金を保証する(適切な債権のみが対象となる) |
請求代行サービスは従業員の負荷を低減し、場合によっては未回収リスクも減らせるという大きなメリットがあります。一方で費用がかかる、請求業務のノウハウを獲得できないというデメリットもあります。導入の際にはコストはもちろん、サービス内容や自社システムとの相性も考慮しましょう。
売掛債権担保融資(ABL)
売掛債権担保融資とは、企業が保有する売掛債権や在庫などを担保にした融資です。銀行や信用金庫、消費者金融などが取り扱っています。担保にできる不動産がない中小企業でも利用できるのが大きなメリットです。また、売掛債権の支払期日前に資金調達ができるため、キャッシュフローを効率的に改善できます。利息は発生しますが、後述するファクタリングの手数料と比べると低めです。
一方で、ファクタリングに比べると時間がかかる、取引先が倒産すると売掛債権の担保としての価値がなくなるなどのデメリットもあります。
売掛債権担保融資では、一般的な売掛債権の他、賃料債権や運送料債権、機械、貴金属、ブランド品、農産物なども担保になり得る点がポイントです。担保手法には通常、譲渡担保が採用されます。これは担保の所有権を債権者に移転し、弁済後に所有権を戻す仕組みです。
買取型ファクタリング
ファクタリングは売掛債権を利用した資金調達手段で、買取型ファクタリングと保証型ファクタリングに分けられます。買取型ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらう仕組みです。通常、売掛債権を現金に換えるには支払期日まで待つ必要がありますが、買取型ファクタリングを利用すれば支払期日よりも前に資金を調達できます。
また、ファクタリングの契約後に取引先が倒産した場合、原則として損失はファクタリング会社が負うことになるため、未回収のリスクも低減可能です。ただし、利用には手数料がかかります。
買取型ファクタリングは契約形態によって、さらに「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」に分けられます。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社が契約する仕組みです。大まかな流れは以下の通りです。
1.売掛債権が発生する
2.利用者とファクタリング会社の間で契約を行う
3.ファクタリング会社が売掛債権額面から手数料を引いた金額を利用者に支払う
4.取引先から利用者に代金が支払われる
5.利用者がファクタリング会社に代金を支払う
2社間ファクタリングは利用者とファクタリング会社が契約する仕組みであり、取引先は関与しません。そのため、取引先にファクタリングの利用を知られないというメリットがあります。また取引先が関与しない分、スピーディな資金調達が可能で、場合によっては申し込み当日に入金されます。
ただし、ファクタリング会社の背負うリスクが大きくなるため、手数料は高めに設定されることが多いです。少しでも手数料を減らしたい場合は、次にご紹介する3社間ファクタリングの利用を検討するのも方法の一つです。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社、そして取引先の3社が契約する仕組みです。大まかな流れは以下の通りで、2社間ファクタリングとは少し異なります。
1.売掛債権が発生する
2.取引先に売掛債権の譲渡を通知し、承諾を得る
3.利用者とファクタリング会社、取引先で契約を行う
4.ファクタリング会社が売掛債権額面から手数料を引いた金額を利用者に支払う
5.取引先がファクタリング会社に代金を支払う
2社間ファクタリングとの主な違いは、取引先の承諾が必要なことと、ファクタリング会社に支払いを行うのが取引先になることです。取引先の承諾が必要な分、入金に時間がかかります。ただし、売掛債権の存在をファクタリング会社が取引先に直接確認できる分、ファクタリング会社の背負うリスクが低くなるため、手数料は低くなることが多いです。
保証型ファクタリング
保証型ファクタリングは、取引先の倒産などで売掛債権が回収できなくなった場合に、ファクタリング会社が代わりに代金を保証してくれるサービスです。
利用者はファクタリング会社に保証料を支払い、ファクタリング会社は取引先が倒産した際に利用者に対して代金を支払います。ただし、取引先が滞りなく代金を支払ってくれた場合、ファクタリング会社に支払った保証料は戻ってきません。万が一の際に備えて加入する、掛け捨ての保険のようなものと考えておきましょう。
保証ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社間での取引です。取引先に利用が知られることはありません。また、保証金額には上限が定められます。例えば売掛債権が300万円あっても、保証上限額が200万円の場合は、代金が回収できなくなってもファクタリング会社からは200万円しか受け取れません。保証料および保証上限額は、取引先の信用力に左右されます。取引先の信用力が高く、未回収リスクが低いとファクタリング会社が判断すれば、有利な条件で契約できます。
なお、保証型ファクタリングではどの取引先の売掛債権に保証を付けるかを選択可能です。売掛債権額が大きく、未回収時に自社への影響が大きい取引先や、与信情報が乏しい新規取引先などに優先的に保証を付けることで、効率的にリスクを減らせます。
まとめ
売掛債権とは、掛取引によって発生した代金を受け取る権利のことです。売掛債権は大きく「売掛金」「受取手形」「電子記録債権」に分けられます。
売掛債権の仕組みは請求業務の負担を減らし、取引先の幅を広げられる一方で、売り手企業はキャッシュフローが悪化しやすくなる他、未回収リスクを抱えることになります。未回収リスクは事前の与信管理などによってある程度は減らせますが、完全にゼロにすることはできません。万が一支払いが行われなかった場合は、法的手段も視野に入れましょう。
未回収リスクを減らす手段は複数ありますが、中小企業から大企業まで利用しやすいのは買取型ファクタリングです。未回収リスクはファクタリング会社が負ってくれる上、2社間ファクタリングなら取引先の承認も必要ありません。
株式会社Mentor Capitaは、最大買取率98%、審査通過率92%(2024年1月~2024年12月実績)の実績を誇るファクタリング会社です。取引実績年間3,000件以上で、業種別に適したプランをご提案します。最短即日で資金調達が可能な他、他社で断られた経験がある場合にも対応できる可能性があります。売掛債権の未回収リスクを減らしたい、資金繰りを改善したいといった場合は、ぜひ一度ご相談ください。